“余りパーツ”だけでここまで出来る!古いSCOTTフレームを復活させた、コスパ最強のDIY組立術

ガレージの隅で眠る、昔乗っていたロードバイクのフレーム。そして、カスタムのたびに増えていく“余りパーツ”の箱。サイクリストなら、誰しも一度は「これで一台、組めるんじゃないか?」と夢想したことがあるのではないでしょうか。
この記事は、そんな思いつきを現実に変えた、一台のSCOTT AFD SPORT(2004年モデル)再生プロジェクトの全記録です。
手元にあった8速コンポや中古パーツを最大限に活用し、足りない部品は格安で調達。「あるものを活かす」をテーマに、コストを抑えながら、驚くほど走れて見た目も楽しい一台を組み上げました。
これは、最新パーツを揃えるのとは全く違う、知恵と工夫と情熱の物語。あなたのパーツボックスにも眠る可能性を、一緒に探してみませんか?
2012年に複数回投稿をまとめた記事です
SCOTT AFD SPORT(2004年モデル)復活計画
以前乗っていたロードバイク、SCOTT AFD SPORT(2004年モデル)を再び乗れる状態に組み立て直します。

手元にあるパーツの再利用
カスタム時に残ったパーツを保管していたため、それらを再利用して組み立てを進めます。
ただし、ドライブトレイン関連のパーツは手元にありませんでした。
- STIレバー:3セット(8速用)
- ドロップハンドル:3本
- クランク:8速用
中古パーツの購入
中古パーツ専門店のサイクリーへ足を運び、必要なパーツを購入しました。
今回の組み立ては8速仕様を予定しているため、グレードはあえて低めのものを選びました。

- BB:スクエアテーパー(110mm)
- RD:SHIMANO 2300
- FD:SHIMANO 2300
クランクの回収
義弟に預けていたクランクを無事に回収しました。
足りないパーツの補充
コンポーネント類は揃いましたが、ケーブル(ワイヤー)などの消耗品はこれから購入して揃える必要があります。
- ケーブル:シフト用・ブレーキ用
- チェーン:8速用
- ペダル:とりえず何でもよい
- ライト:前後必要
- 鍵:駐輪時必要なもの
ウエムラサイクルパーツでの購入
当時勤めていた会社が梅田周辺にあったため、仕事帰りにウエムラサイクルパーツで必要な部品を購入しました。

かさむパーツ代
中古品や格安ショップ(ウエパー)を活用しても、細かい部品を揃えると意外と費用がかかります。
部品代は「塵も積もれば山となる」という言葉の通り、侮れません。
目立つカラーパーツの選択
アウターケーブルは目立つ色を意識して、金色を選びました。
組立作業の開始
週末を利用して、少しずつ丁寧に組立作業を始めました。
ハンドルとサドルの取り付け
作業台を持っていなかったため、自転車をひっくり返して作業できるように、まずハンドルとサドルを先に取り付けました。

クリーニング作業
組み立てを始める前に、汚れを丁寧に落としました。
組み立て後は掃除がしづらくなるため、事前のクリーニングは重要です。
ボトムブラケット(BB)の取り付け
最初にボトムブラケット(BB)を取り付けました。

グリスのたっぷり塗布
ネジ山には十分な量のグリスを塗布し、はみ出した部分は丁寧に拭き取って仕上げました。
リアディレイラー(RD)の取り付け
リアディレイラーの取り付けは、5mmのアーレンキー一本で行えます。
なお、現行モデルでは4mmアーレンキーの場合もありますので、ご注意ください。(2024年現在)

以前使っていたSHIMANO 2200シリーズはケーブル止めが六角ナットだったので、別途工具が必要でした
クランクの取り付け
クランクはボトムブラケット(BB)にボルトでしっかりと固定して取り付けます。

アクスルボルトの取り付け
スギノ製のアクスルボルトを使用しました。
このボルトは8mmのアーレンキーで締め付けることができます。

スギノアクスルボルトは、2個500円でした
作業時間はここまでで約30分
写真を撮りながら進めていますが、ネジを締めるだけの作業なので、順調にスムーズに進みました。

ステムの交換
最初に仮で50mmのステムを取り付けていましたが、極端に短く感じたため、100mmのステムに交換しました。
後半戦のスタート
ここからは、時間を要する作業が続いていきます。
STIレバーの取り付け
部品が増えてきて自転車を逆さまにすると不安定になるため、まずSTIレバーを取り付けて自立しやすい状態にしました。

5mmアーレンキーでの固定
レバー横のスリットに5mmアーレンキーを差し込み、しっかりと固定しました。
自転車らしさが増す瞬間
クランクとSTIレバーを取り付けると、一気にロードバイクらしい姿に変わり、見た目が引き締まります。

ブレーキキャリパーの取り付け作業
ブレーキキャリパーの取り付けを完了いたしました。

ブレーキシューの新品交換
ブレーキシューが摩耗していたため、安全確保の観点から新品に交換しました。
このタイミングでの交換により、制動力の不安もなくなり、安心して走行できる状態になりました。
フロントディレイラーの取り付け作業
フレームにFD台座がなかったため、バンド式のフロントディレイラーを使用して取り付けを行いました。
丸パイプの形状に合わせて、しっかりと固定できるタイプを選定しています。

フロントディレイラーの取付位置調整|クランク構成に合わせて変更
今回のフロントディレイラー(FD)取り付けでは、チェーンリングの構成に合わせて位置を調整する必要がありました。
以前はトリプルクランクだったため、FDの取り付け位置もそれに合わせた高さでしたが、
今回はダブルクランクへの変更により、前回の取付痕とは異なる位置にセットすることになりました。

チェーンリングのサイズや枚数が変わると、FDの高さや角度も変わるため、
チェーンとのクリアランスや変速性能を確保するための微調整が重要になります。
FDを取り付ける前にチェーンの長さを測った方が楽だと気が付きました
チェーンの取り付け作業
チェーンの長さを調整し、チェーンカッターを使用して切断したうえで、取り付けを行いました。

チェーンの初期グリスによる油汚れにご注意ください
チェーンには初期状態でグリスが多く含まれているため、不用意に触れると手や周囲が油で汚れる可能性があります。
作業の際は、十分にご注意ください。
ケーブルの取り付け作業
ケーブルの長さを調整したうえで、取り付け作業を行いました。

作業中は両手が塞がっていたため、記録用の写真は撮影できませんでした。
カラーカスタムの実施
金色のケーブルを採用いたしましたが、視認性にどの程度影響するかが気になるところです。
後半作業に要した時間
後半戦の作業は調整や試行錯誤を重ねる工程が多く、完了までに約2時間半を要しました。
仕上げ作業の実施
午前中にコンポーネント類の取り付けを終えたため、手洗いを済ませて昼食をとった後、仕上げ作業に取りかかりました。
バーテープの巻き付け作業
バーテープには、視認性の高いオレンジ色を選定し、巻き付け作業を行いました。

視認性を考慮したカラー選定
対向車などからの視認性を高めるため、目立ちやすい色を選択いたしました。
バーテープ巻き作業への集中
バーテープの巻き付け作業は集中力を要するため、作業中は写真を撮影する余裕がありませんでした。
仕上がりは予想以上に目立ち、満足のいく結果となりました。

不足部品の調達とタイヤの買い替え
手持ちの28cタイヤはクリアランスが不足していたため、使用できず買い替えを決定しました。
あわせて、その他の不足部品も調達するために外出いたしました。
タイヤの選定|シンプルな色使いと定番モデルを採用
バーテープなどでカラーアクセントを加えたため、タイヤはシンプルな色使いでまとめることにしました。
選んだのは、コストパフォーマンスと耐久性に優れた定番モデル「ビットリア ザフィーロ」。
落ち着いたブラックカラーで、全体のバランスも良く仕上がりそうです。

組立て作業の完了
今回のバイクは、身内が短距離の移動に使用する予定があったため、組立てを行いました。
試乗による動作確認
組立て作業を終えたため、問題の有無を確認する目的で試乗を行いました。

部品構成の違いによる乗り心地の変化
今回の組立では、以前とは異なる部品構成となったため、乗り心地に明らかな変化があり驚きました。
体感としては、以前よりも快適になっているように感じられます。
最終確認と増し締め作業の実施
自転車の動作に問題が見られなかったため、各部のネジを丁寧に増し締めし、組立て作業を完了いたしました。
余剰部品の再利用による組立て
手元にある余剰部品を活用し、可能な限り費用を抑えてロードバイクの組立てを行いました。
消耗品にかかる予想外の費用
消耗品類は必要不可欠なため、個々の金額は小さくても、結果的に思いのほか費用がかさみました。
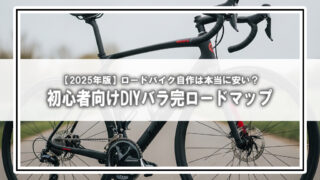
まとめ
ホコリをかぶっていた古いフレームと、箱の中で眠っていた余りパーツたち。それらが再び集い、一台のロードバイクとして走り出す──。今回のSCOTT再生プロジェクトは、まさにDIYの原点とも言える楽しさに満ちていました。
この挑戦を通じて得られた、3つの大きな気づきを共有します。
- 「あるものを活かす」は、最高のクリエイティビティ 限られたパーツの中で「どうすれば形になるか?」と知恵を絞る過程は、パズルのようで非常に楽しいものでした。新品を揃えるだけでは味わえない、自分だけのマシンを作り上げる満足感があります。
- 消耗品の費用は侮れない メインパーツが揃っていても、ケーブル、チェーン、バーテープ、タイヤといった消耗品を新調すると、意外な出費になります。「塵も積もれば山となる」を実感した、リアルな教訓でした。
- 古いフレームでも、乗り味は“蘇る” 同じフレームでも、BBやクランクなど、組み合わせるパーツによって乗り味は驚くほど変わります。今回、想像以上にしっかりとした乗り心地が復活したことは、大きな発見であり喜びでした。
あなたのガレージにも、再生を待つ“主役”たちがいませんか?この記事が、あなたの「もったいない」を「楽しい」に変える、新たなDIYプロジェクトへのきっかけとなれば幸いです。






