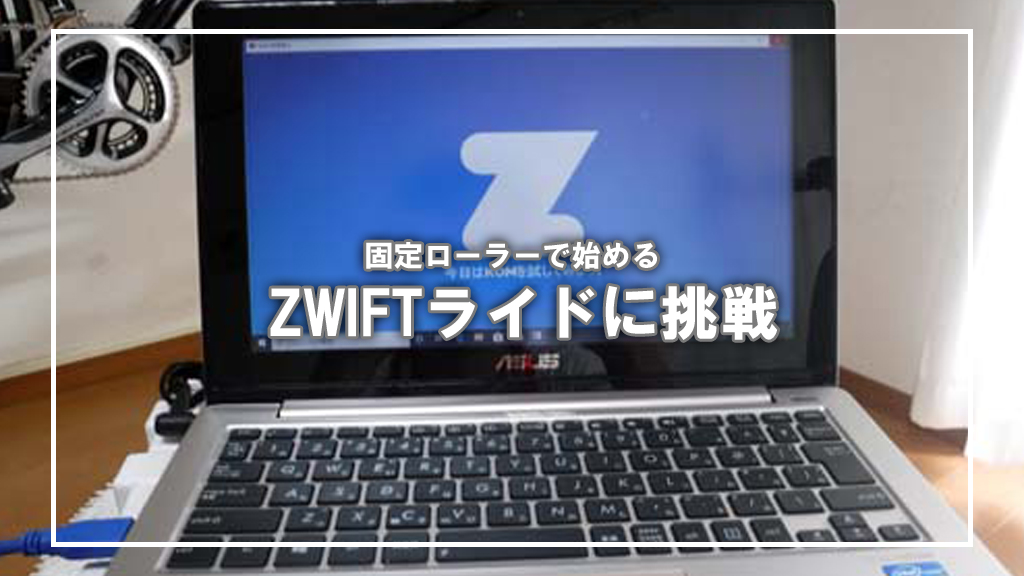「ロードバイク業界は衰退?」有名店の閉店ニュースも…ブームが終わり、今起きている3つの変化とは
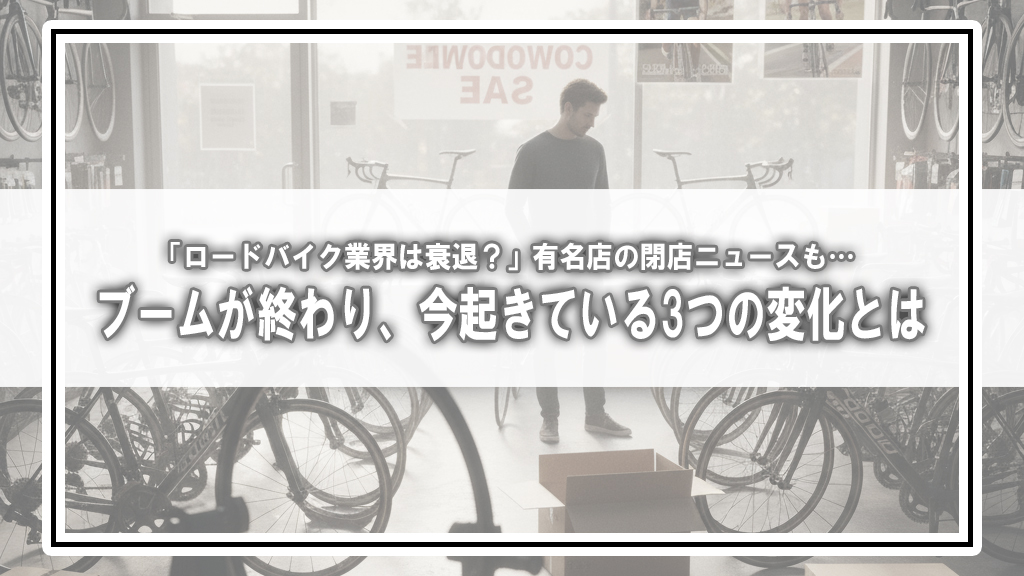
「20代後半からロードバイクを始め、今が一番楽しい時期なのに、業界が縮小していくのは寂しい…」
最近、ある大手ロードバイク専門のECサイトが事業を終了するというニュースが流れ、多くのサイクリストに衝撃を与えました。
「ロードバイクのブームは完全に終わったのか?」 「これから機材はどうなる? 業界は衰退してしまうのか?」
こうした不安の声が広がる中、この「業界の縮小」ムードの背景には、単なるブームの終焉だけではない、日本市場特有の根本的な課題が隠されています。
この記事では、ロードバイク業界の「今」を、様々な角度から分析し、今後の未来について考察します。

なぜ「衰退」と感じるのか?サイクリストが肌で感じる“空気感”
私たちが「業界が縮小している」と感じるのには、いくつかの明確な理由があります。
- 大手・有名店の閉店や縮小
- 今回のECサイトのように、象徴的な存在だった店舗が閉店すると、「業界全体が厳しいのでは?」という印象を強く受けます。
- 専門店の「静けさ」
- 「日曜なのに、ある大型スポーツバイク専門店の店内にお客さんが数人しかいなかった。一方、近所の一般自転車店(ママチャリなどを扱う)は繁盛していた」という目撃談もあります。
- ブームの沈静化
- 2000年代後半や、人気自転車アニメが火付け役となった爆発的なブームは明らかに過ぎ去りました。「サイクリングロードがスカスカになった」と感じる人も少なくありません。
業界で今、何が起きているのか?専門家が指摘する3つの「構造変化」
ブームが去った今、ロードバイク業界は「淘汰」の時期に入り、根本的な「構造変化」に直面しています。
変化1:【二極化】「超高級品」と「ネット通販」への分断
最も大きな変化は、市場の「二極化」です。
あるベテランユーザーは、今の業界を「ユニクロからヴィトンに変わった」と表現します。
- 超高級路線
- 業界の主戦場が、「初めての一台」を売る裾野の広い商売から、「お金に余裕のある既存客に、100万円超えの2台目、3台目を売る」という富裕層向けビジネスにシフトしています。
- エントリー層の消失
- 結果として、ロードバイクの単価は上がっているため、業界の「売上高」自体はそこまで落ち込んでいないかもしれません。しかし、「これから始めたい」という若者やエントリー層が手を出せない価格帯になり、新規の競技人口が先細りしている危険性があります。
変化2:【DIY化】「バラ完はプラモと同じ」と気づいた消費者
かつて専門店の「聖域」だった作業も、情報化によって大きく変わりました。
- オンラインでのパーツ購入
- 30代からZ世代のユーザーは、高額なショップを介さず、「Amazon、楽天、アリエクなどを比較して最安値のパーツを買う」ことが当たり前になりました。
- 工賃の“ボッタクリ”感
- 「『バラ完(フレームからパーツを揃えて組むこと)』は、ガンプラ(プラモデル)を作る程度の難易度でしかないことがバレてしまった」という厳しい指摘もあります。
- DIY技術の一般化
- レースに出るならプロのメカニックが必要ですが、趣味で乗る分には、動画サイトなどで学べば自分で大抵の整備ができてしまいます。結果、「工賃」で利益を上げていた専門店の存在価値が揺らいでいるのです。
変化3:【環境】日本特有の「走りづらさ」という根本的な壁
そして、これが日本市場における最大の問題点かもしれません。
それは、「絶望的に自転車が走りにくい道路環境」です。
ある専門家は、「自転車活用推進法が施行されたにもかかわらず、日本の自転車環境は何も変わらなかった」と断言します。
- 危険な車道、走れない歩道
- 欧州と違い、日本では自転車は「危険な存在」「邪魔者」として扱われがちです。
- 需要の頭打ち
- もし自転車が「安全・快適・速い移動手段」として社会に認識されていれば、ロードバイクへの需要はさらに高まったはずです。
- ガラパゴス化する市場
- この環境が変わらない限り、日本のロードバイク市場は先細り、メーカーは欧州市場だけをターゲットにするようになるだろう、と予測されています。
本当に「衰退」だけなのか?データと熱量に見る“別の側面”
暗いニュースばかりではありません。ロードバイク業界の「熱量」が消えたわけではない、というデータもあります。
- 人気イベントは今も「瞬殺」
- 「ある有名なヒルクライムレースは、今もエントリー開始から1時間で1万人の定員が埋まる」という事実があります。コアな固定客の熱量は、ブーム期以上に高まっているとも言えます。
- 「グローバル市場」は成長予測
- 各種市場レポートによれば、「世界全体」のロードバイク市場は2035年にかけて成長が予測されています。問題は日本の「国内市場」の特殊性(少子高齢化、インフラ)にあるようです。
- 「消耗品ビジネス」としての安定性
- 自転車業界は「本体を売って終わり」ではなく、「消耗品(タイヤ、チェーン等)」や「修理(パンク等)」で成り立つビジネスです。乗る人がいる限り、業界が完全に消滅することはありません。
まとめ:業界は「終わった」のではなく「激変している」
ロードバイク業界は、「衰退している」というよりも、「ブームが終わり、大規模な“変態”の時期を迎えている」と言うべきでしょう。
- 市場は「大衆」から「富裕層」と「DIY層」に二極化。
- 従来の「専門店(ショップ)」のビジネスモデルが崩壊しつつある。
- 日本の「道路インフラ」という根本的な問題が、成長の足を引っ張っている。
近年、ロードバイクの楽しさに目覚めた人にとって、業界の動向は寂しく感じるかもしれません。
しかし、趣味としての楽しさは、業界の規模とは関係ありません。新製品が出なくなることを恐れる声もありますが、世界市場が成長している限り、技術革新が止まることはないでしょう。
私たちにできるのは、この素晴らしい趣味を安全に楽しみ続け、その楽しさを発信し続けることなのかもしれません。