「山手=北」「海手=南」!? 神戸っ子の“方角感覚”がズレてる理由

「山側って、つまり北やろ?」
神戸で育った人にとっては当たり前のこの感覚。
でも、泉州に引っ越してきたら“山手=東”で“浜手=西”という真逆の世界が広がっていた——
今回は、神戸と泉州での“方角のズレ”に戸惑いながらも、
地元の言葉と感覚の違いを体感した記録です。
神戸では、六甲山を背に海を見下ろす地形から、
自然と「山=北」「海=南」という感覚が根付いています。
「右手が東、左手が西」もこの前提があるからこそ成立するわけで、
地元民にとっては“方角=地形”という感覚が体に染みついているのです。
ところが、泉州に来てみると…
「山手」と言えば東側、「浜手」は西側。
だんじりの区分としては通じるけれど、
方角を示す言葉としてはあまり使われないという、
“地元ルールの違い”に直面することになりました。
🧭 この記事でわかること
- 神戸で使われる“山の手=北”という方角感覚の背景
- 泉州での“山手=東”という地元ルールとのギャップ
- ポタリング中に起きた“方角迷子”エピソード
- 地域ごとの言葉の違いが生む“ちょっとした混乱”
- 方角感覚の違いを楽しむ“ローカル文化の面白さ”
【方角の感覚が違う!?】地域ごとの「山手」と「海手」ルール
会話の中で方角を示すとき、地域によって独自の言い方があることをご存じでしょうか?
私が学生時代を過ごした神戸では、「山の手=北」、「海の手=南」というルールが常識でした。神戸っ子にとっては当たり前の感覚で、日常の会話の中でも自然に使われています。
私の地元でも同様に、山の方が北で、海の方が南。これで十分話が通じます。
さらに、京都では「上がる=北」「下がる=南」という表現もあり、とっくり氏とポタリングに行くときも、自然とこの言い回しで方角を話すことができます。「右手が東」「左手が西」という感覚も、このルールがあるからこそ成り立ちます。
しかし、現在住んでいる泉州地域では、このルールが大きく変わってしまいます。
【泉州の方角ルール】「山手=東」「浜手=西」の違和感
泉州では、「山手=東」、「浜手=西」となります。
もともと泉州に住んでいる人にとって、「山手」「浜手」は方角というよりも、だんじりの区分を表すために使われることが多く、方角を示すために頻繁には使いません。しかし、私にとってはこれが大問題!
子どもの頃から、「山の方へ向かえば北」「海の方へ向かえば南」という感覚が体に染みついているため、ポタリングなどで出かけると、どちらの方向へ進んでいるのか分からなくなることがあります。
会話の中でも、「今話している『山手』ってどっちのこと?」と考え込んでしまうことも…。
【少しずつ慣れてきたけれど…】
泉州での生活にも慣れ、地元のルールに馴染んできたつもりですが、それでも時々混乱してしまいます。
地域によって違う方角の感覚。これは住む場所が変わると意外と厄介な問題かもしれませんね。
“方角のズレ”が生む、ちょっとした混乱とローカルの味わい
神戸では“山が北”が常識
六甲山と神戸港という明確なランドマークがあるからこそ、
「山の手=北」「海の手=南」という感覚が自然に身につく。
地図を見なくても、体が方角を覚えているというのが神戸っ子の強みです。
泉州では“だんじり区分”が優先される
一方、泉州では「山手」「浜手」は方角というより“祭りの区分”。
「山手の町会」「浜手のだんじり」など、
地元の人にとっては“文化的な分類”として使われている印象です。
ポタリング中に“方角迷子”になることも
神戸感覚で「山の方へ行けば北やろ」と思って走っていたら、
実は東に向かっていた…というズレが発生。
「あれ?太陽の位置おかしくない?」と気づくまでに時間がかかるのも、
地元ルールの違いを体感する面白さのひとつです。
ご当地ルールで方角を指す言葉一覧
神戸や泉州のように「地形や文化に根ざした“ご当地方角ルール”」を持つ地域の例を、方角の呼び方・意味・地域・マイナー指数(★が多いほど全国的に知られていない)でまとめてみました。
| 呼び方 | 意味・背景 | 主な地域 | マイナー指数 |
|---|---|---|---|
| 山の手/浜の手 | 山側=北、海側=南。六甲山と神戸港の地形に由来 | 神戸市 | ★☆☆☆☆ |
| 山手/浜手 | 山手=東、浜手=西。だんじり文化の区分にも使われる | 泉州(岸和田など) | ★★★☆☆ |
| 表参道/裏参道 | 神社の正面(南)を「表」、北側を「裏」とする。地元では方角の目印に使われる | 京都・奈良の神社周辺 | ★★★★☆ |
| 上町/下町 | 上町=北、下町=南。江戸時代の地形と身分制度に由来 | 東京(中央区など) | ★★☆☆☆ |
| 表六甲/裏六甲 | 表=神戸市街地側、裏=北側の山間部。登山やドライブで使われる | 兵庫県六甲山周辺 | ★★★★☆ |
| 山側/川側 | 山側=北、川側=南。川沿いの町で使われることがある | 岐阜・長野など | ★★★★☆ |
| 海側/陸側 | 海側=南、陸側=北。漁港の町で使われることが多い | 三重・和歌山など | ★★★☆☆ |
| 表通り/裏通り | 表=駅側、裏=山側など、地元の生活動線に基づく | 全国の商店街など | ★★★★☆ |
📝補足ポイント
- 神戸と泉州の違いは、まさに「山がどっちにあるか」で感覚が真逆になる好例です。
- “表・裏”文化は、神社や城下町に多く、観光案内でも使われます。
- “上町・下町”は東京だけでなく、京都や大阪でも歴史的に使われてきました(ただし意味が異なる場合も)。

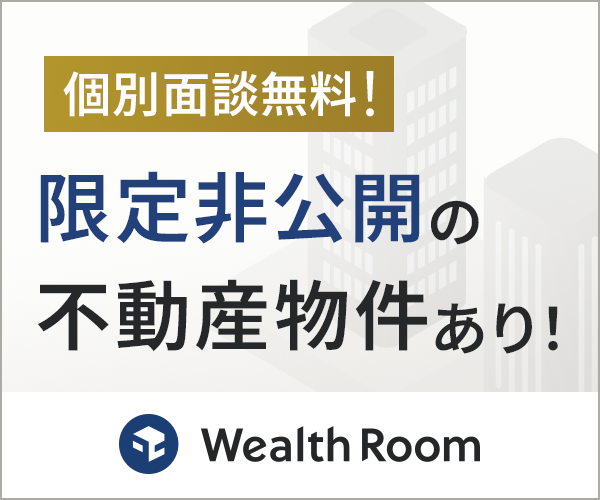

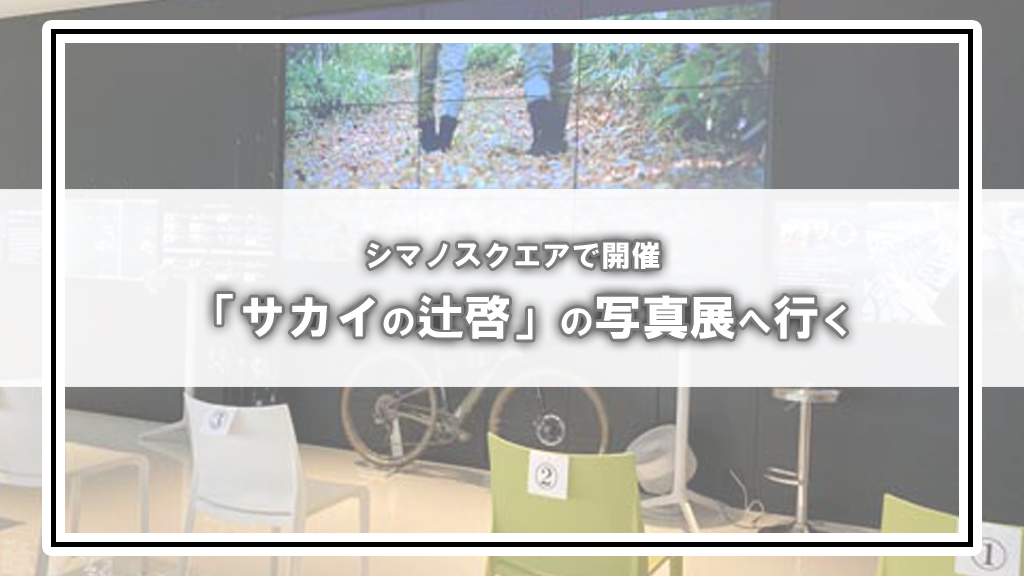
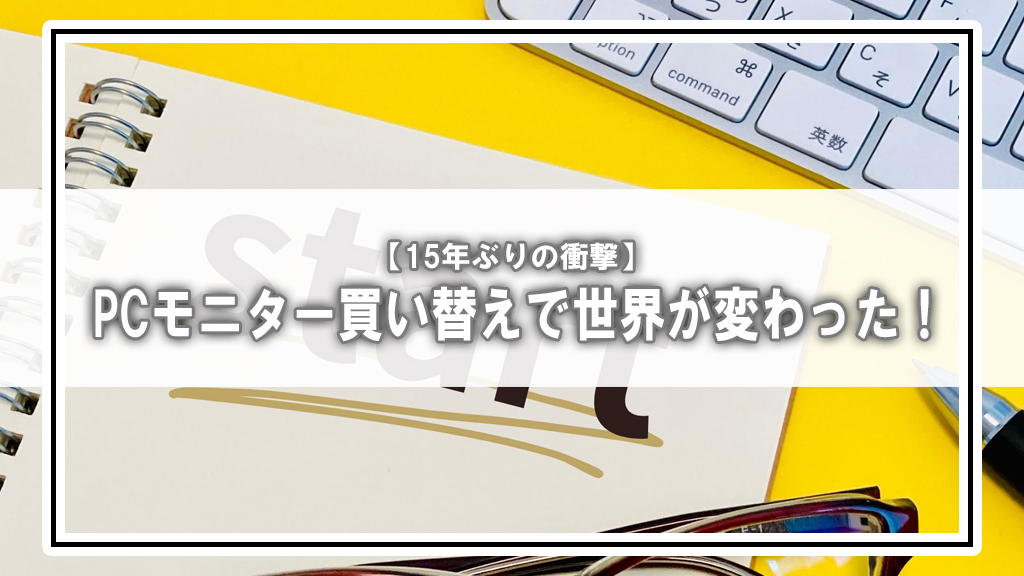
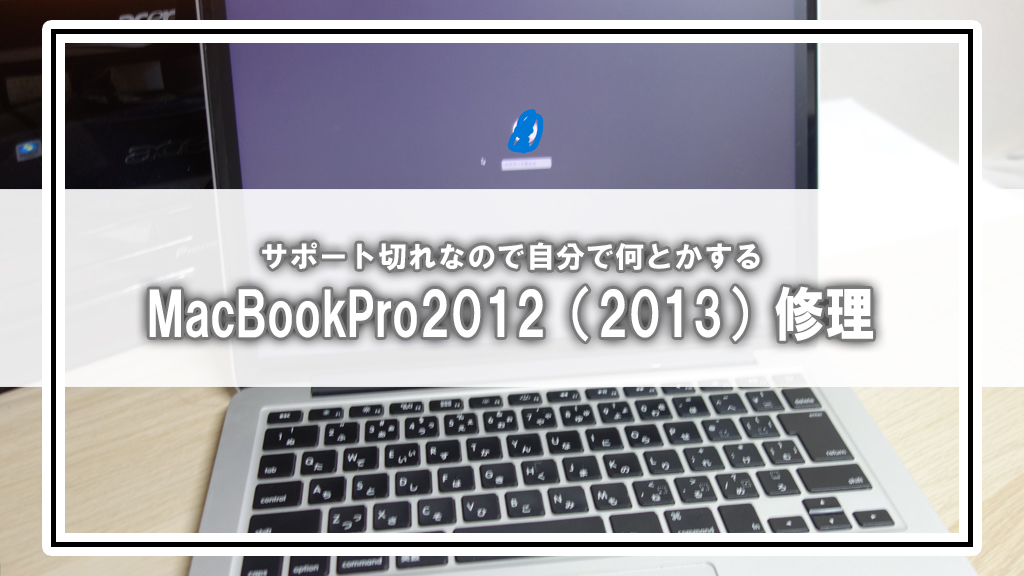
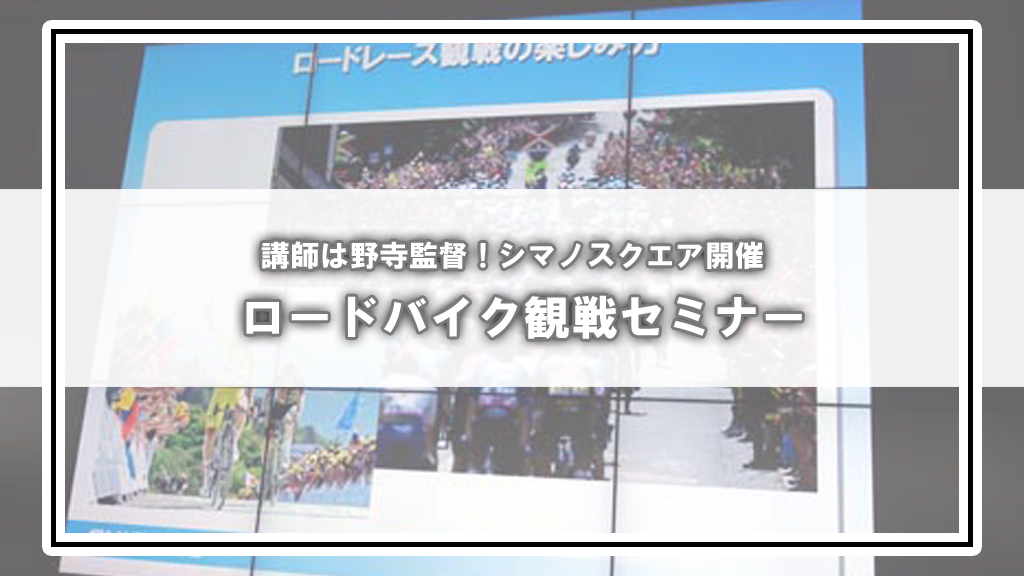
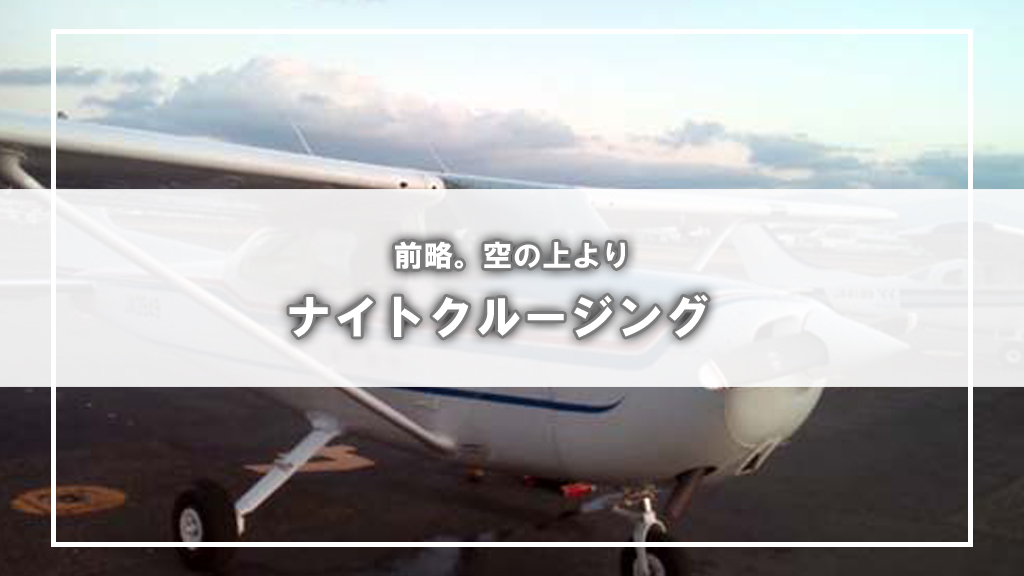

私の場合、岐阜県出身の親戚達と話をする時に、似たようなことが起こります。
方向を表すのに左右前後ではなく東西南北で話されるので、方角を理解していないと話に付いてけません。
鹿児島では大隅と薩摩で東西が変わってしまいますね。
埼玉は関東平野の真ん中で海がないです。
神戸の北が山と違い、目印になるものが
ありません。最初すごく戸惑いました。
> ヨッシーパパ様
なるほど、東西南北で言われると、はっきり地理を理解していないといけないのですね。
> moumou様
同じ県内でも、方角の言い回しが変わってしまうのも混乱の原因になりますね。
> hayazou2002様
神戸の感覚で、引越先に目印がないことは、すごく戸惑いますね。