【自転車DIY】BB取り付けで差がつく!固着・ネジ山潰れを防ぐ“プロ級のひと手間”テクニックまとめ
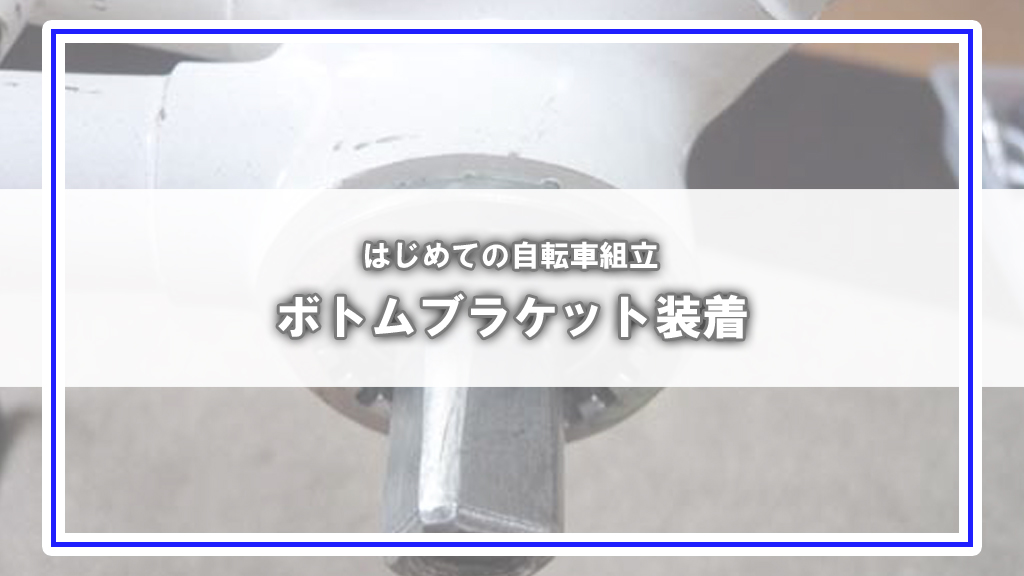
「BBの取り付けなんて、グリス塗って締めるだけでしょ?」
そう思っていたら、ネジ山潰れや固着で後悔することに…。
この記事では、スクエアテーパーBBの取り付け手順・グリスの種類と塗布ポイント・締め付けトルクの注意点・工具の工夫・クランク圧入部のグリス有無に関する実践的な考察などを、DIY視点で詳しく紹介します。
この記事でわかること
- スクエアテーパーBBの取り付け手順と規格ごとの違い
- ネジ山保護のためのグリス塗布と“左右の締め順”の意味
- 固着を防ぐためのアンチシーズや緩み止め剤の使い方
- 工具が外れないようにする工夫とおすすめアイテム
- クランク圧入部にグリスを塗るべきか?実践から導いた答え
はじめての自転車組立
一応書籍などで基本的な知識は学んでいますが、あまり順序通りに進められるタイプではないため、作業手順は自分なりの思いつきで進めている部分もあります。
BB取付
まずはボトムブラケット(BB)を取り付けることにしました。
後から取り付けようとすると、他のパーツが干渉しそうだったため、先に作業しておく方がスムーズだと判断しました。
スクエアテーパー

左右注意
取り付けの際は左右を間違えないよう、パーツにしっかりと表記がされていました。
ボトムブラケットの規格について
ボトムブラケットにはいくつか規格があり、今回はJIS規格のものを使用しています。
イタリアン規格や、最近の大径タイプはサイズが異なるとのことですが、名前を聞いたことがある程度で、実物はまだ見たことがありません。
なお、ホローテックのような規格は構造が異なるため、取り付け工程もまったく別になります。
グリス
取り付け前には、ねじ山や接触面にグリスをたっぷりと塗布しておきます。
これにより、固着や異音の防止に効果があるとされています。
グリスは質の良いもの
今回取り付けたのは、シマノ製コンポーネントの最上位モデル「DURA-ACE」です。

グリスを塗るシーンも撮ろうと思っていたのですが、手ブレしてしまい、うまく撮れていませんでした。残念…。
BB取付
それでは、ボトムブラケット(BB)をフレームに取り付けていきます。
とりあえず左から
手順としてこれが正解かは自信がありませんが、今回は左側から取り付けていくことにしました。

専用工具必須
この作業は専用の工具がないと、手だけで回すのは非常に難しいです。

シマノ製
そこで、今回使用した工具はシマノ製の「TL-UN74」です。

こんな感じで使います。
使いにくい工具
こちらの側は、後ほど再度締め直す必要があるため、まずは手で軽く固定できるところまで回します。
ただ、この工具は少し使いにくく、作業がやや難しいと感じました。
対策あり
対策については、記事の後半部分に詳しくご紹介していますので、ぜひそちらをご参照ください。
ボトムブラケット(BB)は両側からしっかりと挟み込むようにして締め付けます。
作業の手順は守ったほうが安全です。
まずはテンションがかかっていない左側を取り付けていますが、反対側を取り付けないと無限に回ってしまう状態になります。

右側は締め込むことで適切なテンションがかかるため、しっかりと固定する必要があります。
TL-UN74は使いにくい
シマノ製の工具「TL-UN74」を使用する場合、工具をボトムブラケット(BB)にしっかり固定できないため、作業がやややりにくく感じられました。
テクニック紹介
そこで、いつもお世話になっている自転車店の店長さんから教わった便利な小技を活用してみることにしました。

ワッシャーを使う
クランクを取り付けるネジと専用工具(TL-UN74)よりも一回り大きいワッシャーを使用します。
物理的に固定する
専用工具(TL-UN74)をボトムブラケット(BB)のネジ山に合わせて装着し、その上からワッシャーを当ててネジでしっかりと固定します。

取り付けると、このような状態になります。
これで滑らない
この方法で、モンキーレンチなどを使った際に力が逃げず、しっかりと回すことができます。

締め付け作業の完了
これでボトムブラケットの締め付け作業が完了しました。
しっかりと固定されているか最終確認を行い、次の工程に進みましょう。

仕上げは丁寧に
グリスをしっかり塗るとどうしてもはみ出してしまうため、作業後は丁寧に余分なグリスを拭き取っておきます。
はみ出したまま放置すると見た目が悪くなるだけでなく、汚れの原因にもなりかねません。(あくまで私の考えですが)
左側のボトムブラケットも確実に締める
反対側の左側も、同様の手順でしっかりと締め付けます。
左右の締め付けが均等であることが、正しい取り付けには欠かせません。
外すときにも役立つテクニック
この小技は、ボトムブラケット(BB)を外す際にもぜひ活用したい方法です。
長期間固定されたままだと固着してしまい、専用工具(TL-UN74)だけで力を入れると、最悪の場合ネジ山を傷めてしまうことがあります。
ネジ山がつぶれてしまうと、取り外しが非常に困難になるそうです。
しかし、ちょっとした工夫をすることで、こうした最悪の事態を避けることが可能です。
工具選びのポイント:BBB製などの一体型レンチがおすすめ
工具を選ぶ際は、パークツールやBBBなどのメーカーから販売されている、一体型のレンチタイプのものがおすすめです。
これらの工具は一本で複数の作業に対応できるため、これから購入される方には特に使い勝手が良いでしょう。
“BB取り付けは、ひと手間で寿命が変わる”——グリス・工具・締め順までこだわるDIYメンテの極意
今回の作業では、スクエアテーパーBBの取り付けにおいて、グリスの塗布量・締め付け順・工具の工夫・圧入部の処理など、細部にこだわることで固着やネジ山潰れを防ぎ、長期的な快適性と安全性を確保することができました。
“ただ締めるだけ”ではなく、“どう締めるか”が差を生むのがBBメンテの奥深さ。
“走って・締めて・考えて・守る”——そんな気持ちになれる、自転車DIYの体験記でした。
工具がズレると“ネジ山が死ぬ”
TL-UN74は、BBに差し込むだけの構造。
そのまま力をかけると、工具が外れてネジ山を潰す危険性が高い。
そこで、ワッシャーとクランクボルトで工具をBBに固定する方法が効果的でした。
グリスは“たっぷり”が正解
ネジ山には、焼き付き防止と固着防止のためにグリスをしっかり塗布。
「後で外せなくなるくらいなら、今しっかり塗っておこう」という意識が大切です。
ネジの向きは“左右で違う”
JIS規格では、右ワンが逆ネジ(左回しで締まる)、左ワンは正ネジ(右回しで締まる)。
イタリアン規格は両方正ネジなので、作業前に規格を確認することが重要です。




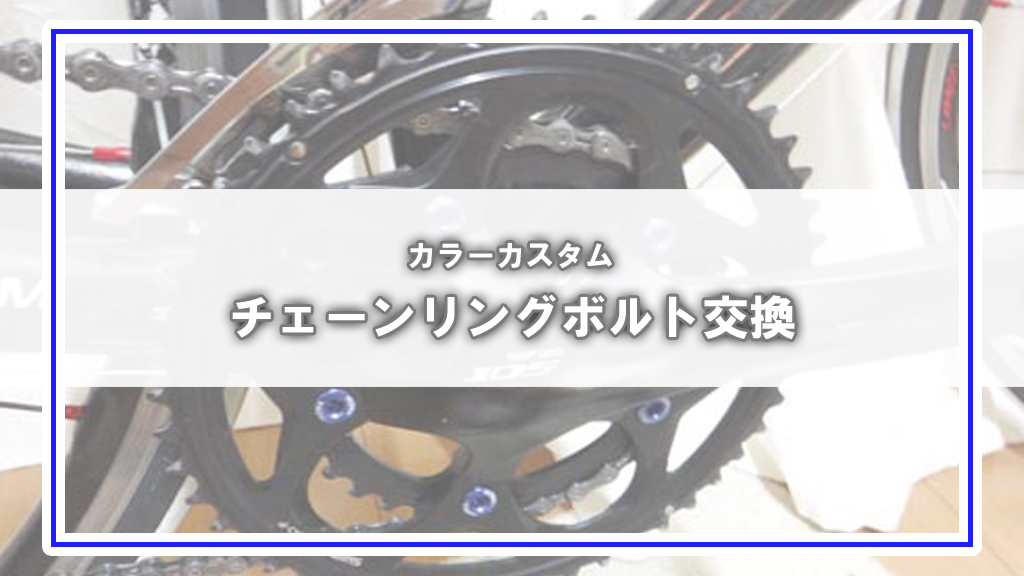
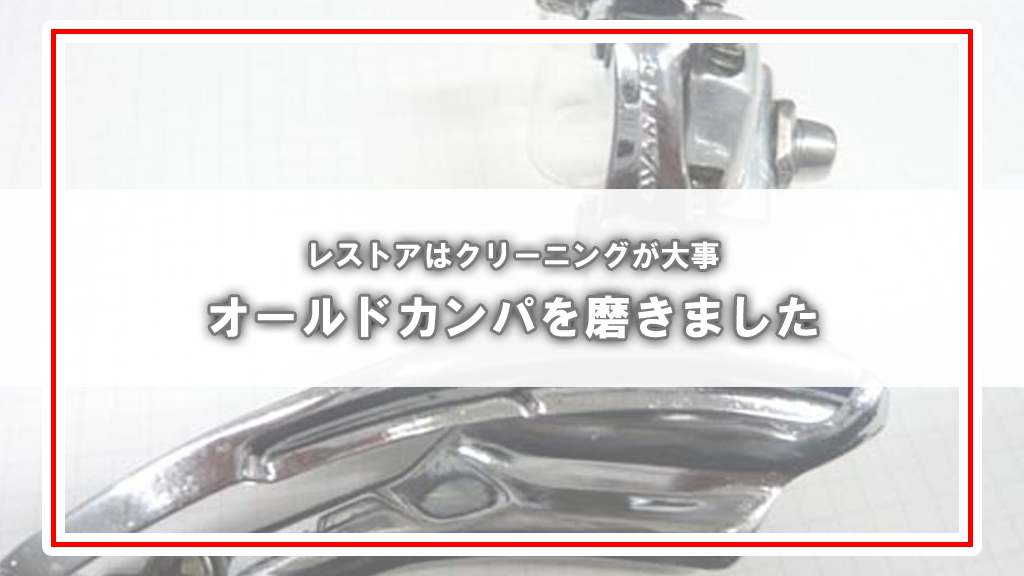


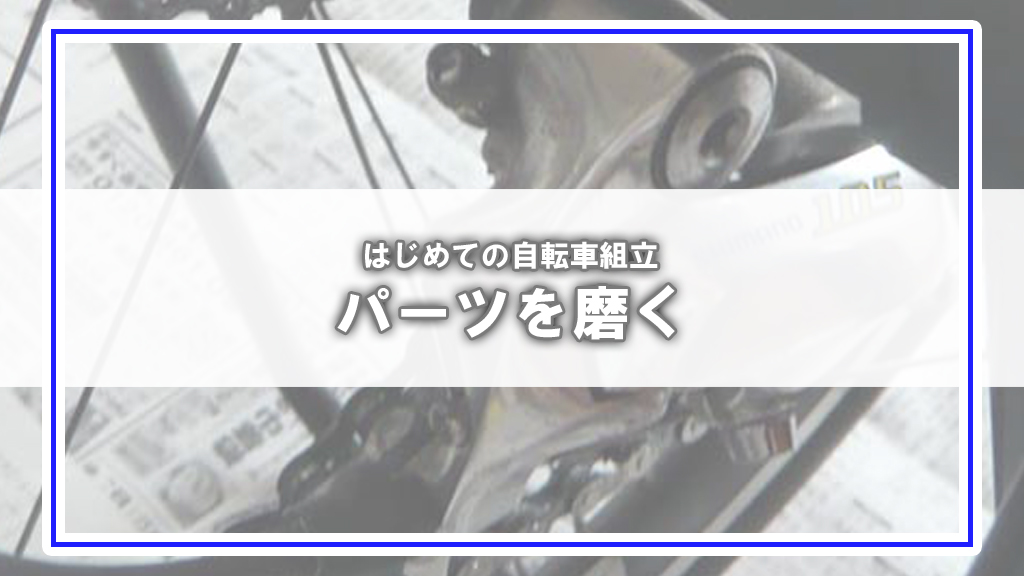
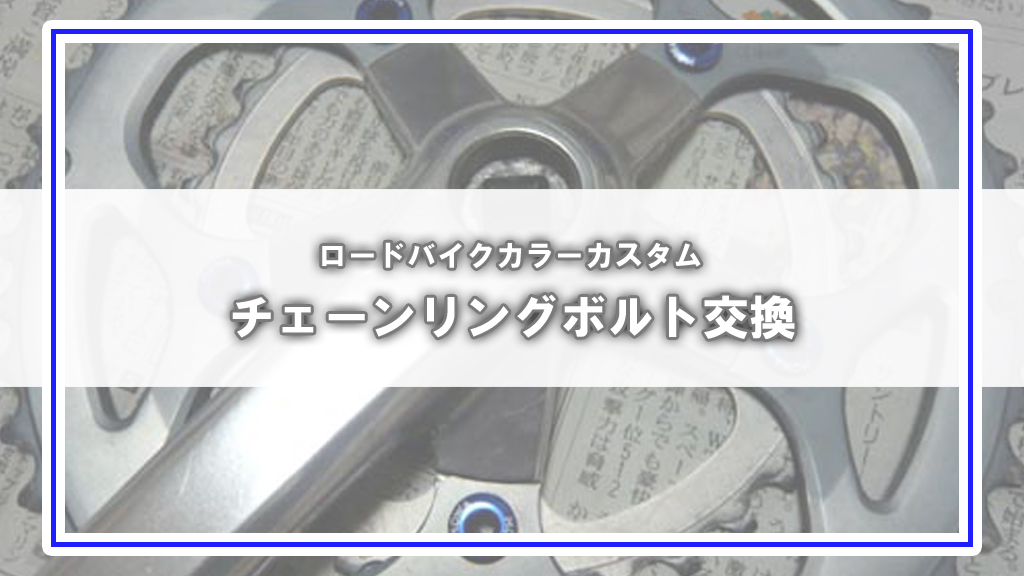
おおっ、すごい技ですね。
オクタリンクのBBまだ使っているんですよ!(^^)!
> tsun様
オクタリンクも同じ工具で外すのでしたら、この技使えますね。
ワッシャー1枚を工具箱にいれておかれると大事な自転車を痛めないと思います。
私の赤い彗星号のBBは
600のカップ&コーンのやつです。
> hayazou2002様
カップ&コーンも外す時にテクニックが要りそうですね。