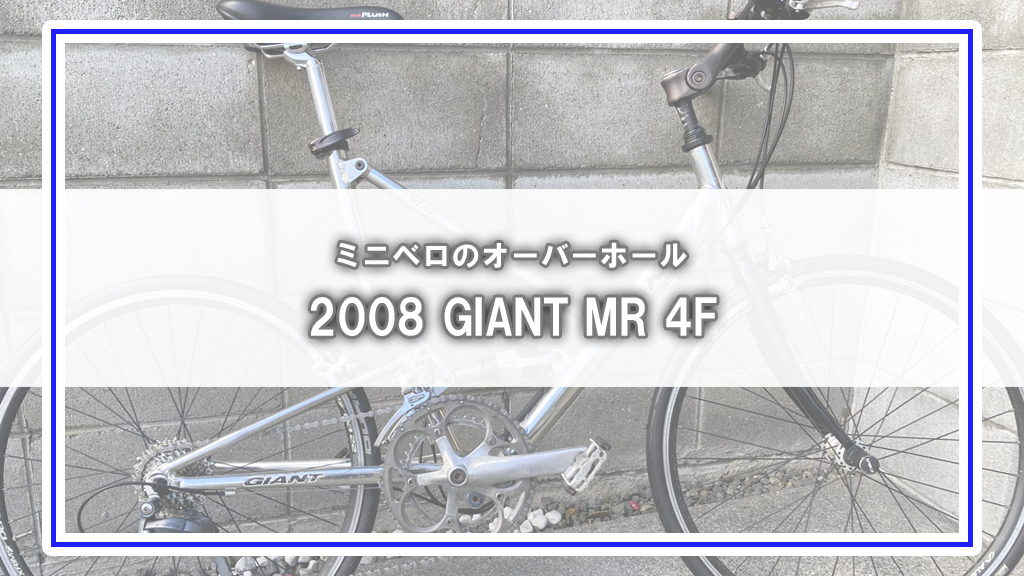バラして、磨いて、組み直す——3台のバイクから生まれた“再構築ロード”の記録

「このフレーム、まだ使えるかも…」
そんな一言から始まったのは、3台のロードバイクを“部品取り”して1台を再生するという、まるで“自転車版フランケンシュタイン”のようなカスタム計画。
今回は、とっくり氏から譲り受けたバイクをベースに、黒・白・緑の3台からパーツを移植していく“再構築プロジェクト”の記録です。
作業を担当するのは、あ〜やん&みぞおの2名体制。
「このパーツはこっちに」「このホイールはあっちに」と、まるでパズルのようにパーツをやりくりしながら、それぞれのバイクに新たな役割を与えていく。
最終的には、“相方さんのお父さんへのプレゼントバイク”と、“とっくり氏の新たな愛車”が完成する予定です。
🔧 この記事でわかること
- 3台のバイクからパーツを移植する“再構築”の流れ
- コンポ・ホイール・サドルなど、部品のやりくりと判断基準
- 分解・清掃・オーバーホールの手順と注意点
- 固着したBBや汚れたクランクとの格闘エピソード
- “再生バイク”が完成するまでの工程と今後の展望
自転車改造計画
とっくり氏から譲り受けた、使われなくなった自転車を活用して、新たな一台を組み上げるというこの計画。前回考えていた仕様から、少し方針を変更することにしました。
部品をやりくりする自転車の名称
- 黒: 今回譲り受けたベースバイク
- 緑: 丸石ハーフマイラー
- 白: とっくり4号

パーツ移植の内訳
(黒) > (緑)
- 105フルセットのコンポ(トリプル):そのまま移植し、コストを抑える
- フォーク:メッキ処理がキレイなので、使えれば再利用
- ハンドル/ステム:問題なければそのまま使用
(黒) > (白)
- ホイール(CAMPAGNOLO SCIROCCO):タイヤを入れ替えて使用
- サドル:とっくりさんが使いやすかったものをそのまま活かす
(白) > (緑)
- ホイール:タイヤを入れ替えて移植
破棄予定
- 黒のフレーム:カーボンにクラックありで危険
- 緑のホイール:スポーク破損でコスト的に再生は難しい
- その他保管中ホイール:使い道なしのため処分
そろそろ、要るもの・要らないものをしっかり整理しないと怒られそうです(笑)
作業の概要と今後の用途
| バイク | 作業内容 | 完成後の用途 |
|---|---|---|
| 黒 | 分解・パーツのオーバーホール | フレームは破棄 |
| 白 | ホイール交換 | とっくりさんの新愛車 |
| 緑 | 分解・塗装補修・パーツ移植 | 相方さんのお父さまへの贈り物 |
作業期限
| 作業対象 | 期限 |
|---|---|
| 黒 | 今月(6月)中 |
| 緑 | 7月末、遅くとも8月納品予定 |
| 白 | 今週中に完成、とっくり氏の都合次第で納品 |
| その他 | 不要部品は7月末までに処分予定 |
作業上の注意点
- 確認するポイントが多いので、報・連・相(報告・連絡・相談)を忘れずに
- 工具の扱いには注意し、ケガのないよう慎重に
- 足りないパーツがあれば、都度打ち合わせを行うこと
パーツ組み替え
とっくり氏から譲っていただいた自転車のパーツを活用するため、まずは現在のバイクをばらしていきます。
現状のチェック
STI(シフター)
STIレバーはかなり使い込まれており、傷が目立ちます。

フロントディレイラー・リアディレイラー
駆動系パーツであるフロントディレイラーやリアディレイラーは、10年以上前のものですが、室内で保管されていた上に定期的な清掃もしていたおかげで、全体的にまだまだきれいな状態です。


ブレーキ
ブレーキ本体も、見た目はしっかりしていて、十分再利用できそうです。

分解作業スタート
それでは、さっそく分解に取り掛かります。基本的には無理のない範囲で、手順を意識しながらばらしていきます。
チェーンの取り外し
これまではディレイラーまわりから作業を始めて、後からチェーンの扱いに苦労することが多かったので、今回は最初にチェーンを外すところからスタート。

ミッシングリンク
チェーンにはミッシングリンクが取り付けてあるため、専用工具がなくても簡単に外せます。
使用期間は正確には覚えていないのですが、目立った伸びもなく、まだ使えるかもしれませんね。

ワイヤーの取り外し
続いては、ワイヤー類の取り外しに入ります。
まずはテンションがかかっている状態を解消することが大事です。


テンションが抜けるギアの組み合わせ
ディレイラーにかかるテンションを緩めるには、シフトの位置を調整しておくと作業しやすくなります。
具体的には、
- フロントディレイラーはインナー側
- リアディレイラーはアウター側
この状態が、最もテンションがかかっていない組み合わせになります。
ブレーキも忘れずに
ブレーキワイヤーも、リリースレバーを開いた状態で作業するのが基本。ワイヤーにかかる力が抜けているので、安全かつスムーズです。

注意:テンションが残っていると危険
テンションをかけたまま作業を進めると、何かの拍子にパーツが動いてしまい、指を挟んでケガをする可能性があります。実際に、筆者自身も過去にそういった事故を経験しています。
安全第一で作業しましょう。
工具について:5mmアーレンキーがあれば大体OK
シマノのコンポーネントであれば、5mmの六角レンチ(アーレンキー)が1本あれば、大抵のワイヤー調整作業は行えます。
工具選びのポイント
自分でメンテナンスやオーバーホールをするなら、使用頻度の高い工具については質の良いものをそろえておくのがオススメです。
特に、
- 5mmのアーレンキー
- プラスドライバー
この2つは作業中によく使うので、丈夫で手に馴染むものを選ぶと作業効率がぐんと上がります。
確認しながら慎重に作業を進めます
チェーンにはテンションがかかっていたので、まずは外しておきました。また、ワイヤーもゆるめておいたので、万が一の事故につながるような状態にはならないはず……たぶん大丈夫です。
とはいえ、作業中に何かあっては困るので、念には念を入れて、慎重に進めていきます。
まずはクランクから
最も汚れがたまりやすそうな「クランク」から取り外していくことにします。
使用する工具:8mm六角レンチ(アーレンキー)
クランクは8mmの六角レンチを使って固定ボルトを外します。

クランクはネジを外しただけでは取れません
クランクはBB(ボトムブラケット)軸にしっかり差し込まれているため、ただネジを外しただけでは簡単には外れません。もしそれだけで外れる構造だったら、人の脚力でも外れてしまいそうですよね。
クランクを外すには専用工具「コッタレス抜き」を使います
ここで登場するのが、クランクを外すための専用工具「コッタレス抜き」です。

こんな工具です
コッタレス抜きの仕組みは「押し出す」タイプ
工具のネジ部分をBB軸側に押し込むことで、クランクをぐっと押し出す構造です。

細かい使い方については、各メーカーの公式ページなどを参考にしていただけると安心です。(ちょっと他力本願ですが……)
クランクが外れました!
無事に外れました。

……想像以上に汚いです
普段から整理整頓が行き届いている、とっくしさんからすれば信じがたいほど、泥やゴミが詰まっていて驚きました。
「これは、たまにはちゃんとオーバーホールしないとな……」と強く思うほどの汚れ具合です。ここまでゴミが詰まっていると、さすがにパフォーマンスにも影響が出ている気がします。
続々とパーツを取り外していきます
ここから、いよいよ本格的にパーツを外していく作業に入ります。
次はBB(ボトムブラケット)を外します
BBを外すためには、専用の工具「TL-UN74-S」を使用します。
ボトムブラケットは構造上、しっかりと固定されているため、外すには専用工具が必要なんですね。

でも…まさかの固着
いざ作業に取りかかろうとしたのですが、ネジがびくともしません。
完全に固着してしまっているようです。
どうやら、このBBは取り付けてから約10年もの間、一度も緩めたことがなかった様子。
これだけ長い間放置されていれば、固まってしまうのも無理はないですね。
というわけで、BBの取り外しは作業の最後に回すことにしました。
補足:このクランクとBBは「オクタリンク」規格です
ちなみに、今回の自転車に使われているクランクとBBは「オクタリンク」という規格のもの。
最近主流のホローテックIIや中空クランクとは構造が異なり、使う工具も異なります。
続いてはブレーキとディレイラーを外します
次に、ブレーキ本体と、すでにテンションが抜けた状態のディレイラーを取り外していきます。

ブレーキは、アーチの裏側にあるネジを緩めるだけで簡単に外せます。
ディレイラーも、ネジ1本で固定されているだけなので、手間はかかりません。

使用する工具は5mmの六角レンチ
ここでも活躍するのは、5mmのアーレンキー(六角レンチ)。
実は、自転車の多くのパーツは、ネジ1本で固定されていることが多く、工具さえあれば意外と簡単に外せてしまうんです。


シートポストも取り外し
次は、シートポストを外していきます。
ここは少し注意が必要で、メーカーによってネジのサイズが異なる場合があります。
そのため、複数のサイズの工具が手元にあると安心ですね。

作業は順調に進行中!
主要パーツをどんどん取り外していった結果、自転車のフレームだけが残ったような状態に。
「もともとの形」が少しずつ姿を変えていく様子は、ちょっと不思議でワクワクしますね。

分解作業、まだまだ続きます
「ハンドルを外せば、いよいよフレームだけになるぞ!」と意気込んで、作業を進めていきます。
ハンドルの取り外し…のはずが
ここで問題発生。
ステムを外そうとしたところ、ワイヤーが邪魔でうまくいかないことに気づきました。
手順を少し読み違えてしまったようです。
どうやら、STIレバーを先に外しておくべきでしたね。

バーテープを剥がす
一度ステムを戻し、今度はバーテープの取り外しに取り掛かります。

今回使われていたのは白のコルクタイプ。
そのためか、汚れが目立ちやすく、変色も進んでいます。洗えない部分ですし、これは仕方ありません。
粘着力の強いバーテープと格闘しながら、なんとか剥がしきりました。
STIレバーの取り外し
次にSTIレバーを取り外します。

こちらもおなじみ、5mmのアーレンキー(六角レンチ)を使用。
レバーの外側にあるくぼみの中にネジ穴があり、そこにレンチを差し込んで回します。
いよいよBB(ボトムブラケット)再挑戦!
すべての外せるパーツ(アウターストッパーなど)を取り外し、
いよいよ前回固着していて断念したBBの取り外しに再チャレンジです。

まさかのアッサリ?
今回は「フレームが壊れても仕方ない」という気持ちで、思い切って力をかけてみました。
すると、姿勢がうまく決まったおかげで、思ったほど力を入れずに回すことができ、あっさり外れました。
BBの中も汚れがびっしり
外してみると、BB内部には泥や汚れがたっぷりと溜まっていました。
軽く拭き掃除をして、記念撮影。
ついに、フレームだけになりました。

フレームの状態について
一見するとまだ綺麗に見えるフレームですが、実はクラック(ひび割れ)が入っている箇所があります。
カーボン柄のシールで目立たないようにしていますが、ダブルレバー台座の間にクラックが確認できます。

このクラックが入った後も、8年間ほど普通に乗っていたのですが、このフレームは事故の危険性を考えて買い替えたものです。
そのため、今後は廃品回収のタイミングで修復不可能なように処分する予定です。
改めて感じた「定期的なオーバーホールの大切さ」
今回の分解作業を通じて強く感じたのは、
「自転車は、乗った後の掃除はもちろん、定期的なオーバーホールも欠かせない」ということです。
一見キレイに見えていても、内部は思いのほか汚れていたり劣化が進んでいたりするものなんですね。
ホイールを移植します
自転車の分解作業が無事に終わったので、今度はとっくり4号に、取り外したホイールを移植します。
スプロケットの交換作業
とっくり4号は8速仕様ですが、今回バラした自転車は9速だったため、
ホイールごと移植するにはスプロケットを交換する必要があります。
まずはクイックレバーの取り外し
スプロケットを外す前に、クイックリリースレバーを取り外します。
両端にバネが付いているので、バネを無くさないように注意しましょう。

ロックリングリムーバーを使用
スプロケットを外す際は、専用工具(ロックリングリムーバー)を使います。

この工具があると、スプロケットを簡単に外して掃除もできるようになるので、
メンテナンスをする方には、1本持っておくことをおすすめします。
スプロケットリムーバーで押さえる
スプロケットは空回りする構造のため、チェーンが付いたような工具(スプロケットリムーバー)で押さえながら、ロックリングを緩めます。

外したスプロケットは細かいパーツに分かれるので、順番が分からなくならないよう、
きちんとまとめて保管しておきましょう。
(写真があまり使い物にならなかったため、このあたりの行程は割愛します)
9速→8速スプロケットへ
先ほど取り外しておいた8速スプロケットを、ホイールに取り付けます。

シマノ製スプロケットには、1カ所だけ明確に違う突起があるので、
そこを目印にして向きを合わせながら装着していきます。
スプロケット交換、完了!
あとは、先ほどと逆の手順でネジを締め直せば、スプロケットの交換は完了です。

サドルも交換してみたけれど…
ついでにサドルも別のものに交換してみましたが、
見た目だけでいえば、このままでも意外と悪くないのでは?とちょっと思ってしまいました。
ただし、タイヤがかなり傷んでいたため、そちらは交換する予定です。
タイヤ交換を行いました
タイヤ交換の作業は、基本的にはパンク修理の工程とほとんど同じです。
まずは「パンク修理」のように作業開始
今回はチューブを入れ替えるのではなく、タイヤだけを交換していきます。
タイヤレバーを使って外します
タイヤを取り外すときには、専用のレバー(タイヤレバー)を使用します。
少し強引かな?と思うくらいの力で、タイヤの隙間に差し込んでいくのがコツです。

タイヤのテンションを外す
タイヤレバーは通常3本セットなので、3本とも差し込んで順番にずらしていくと、タイヤの張力が抜けて外れやすくなります。

(写真のタイヤの色が違うのは、実は都合4回ほどやり直していて、その中で一番手ブレが少ないカットを選んでいるためです)
チューブを取り外す
タイヤが片側外れたら、中のチューブを取り出します。

タイヤが柔らかい場合はスムーズですが、まれにチューブが張り付いたようになっていることもあるので、丁寧に作業します。
タイヤをホイールから外す
チューブを取り出したら、タイヤ自体もホイールから完全に外します。
(この工程は写真のブレがひどく、何が何だかわからない状態になってしまったため、画像は省略しています)
タイヤの取り付け
ここからは、これまでの作業を逆の手順で進めていきます。
タイヤを取り付ける前に…
装着前には、タイヤの内側にゴミや異物がないかチェックしておくことが大切です。
空気を少し入れる
また、チューブに少しだけ空気を入れておくと、タイヤに収めやすくなります。

これはパンク修理のときと同じポイントですね。
今回はタイヤ4本分を交換
ホイール2セット分、タイヤを4本すべて交換しました。
つまり、パンク修理と同じ作業を4回分やったことになります。

今後について
今後は、シフターのアウターケーブルやバーテープも白か青系に変えてみようかな、と考え中です。
これにて、とっくり氏から譲り受けた自転車の分解作業と、とっくり4号へのパーツ移植作業がひと段落しました。
“使えるものは使い切る”——再構築カスタムで見えてきた、バイクの新しい価値
フレームにクラック? でもパーツはまだまだ現役
黒フレームは破棄予定だけど、105のトリプルコンポはまだまだ使える。
「これ、全部移植すれば1台組めるやん!」という発想の転換がスタート地点でした。
ホイールのやりくりは“コストと状態のバランス”
スポークが曲がっていたり、タイヤが劣化していたり。
「直すより替えた方が早いかも…」という判断も含めて、“使えるもの・使えないもの”を見極める目が問われます。
分解作業は“工具と根気とケガ防止”が命
チェーンはミッシングリンクで簡単に外せたけど、
BBは固着していて全然回らない…!
「壊れてもいいから全力で回す」覚悟で挑んだ結果、意外とあっさり外れたというオチも。