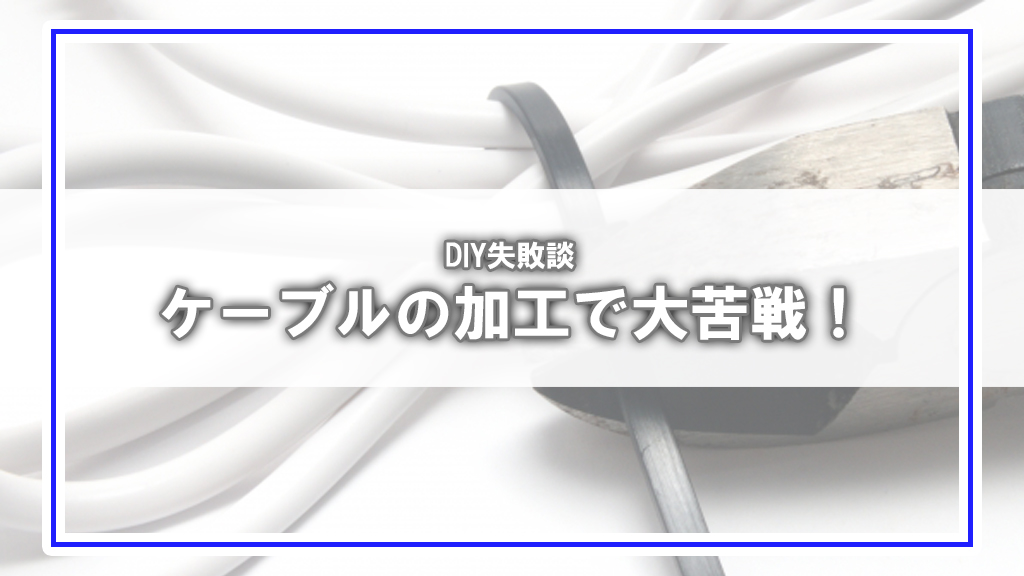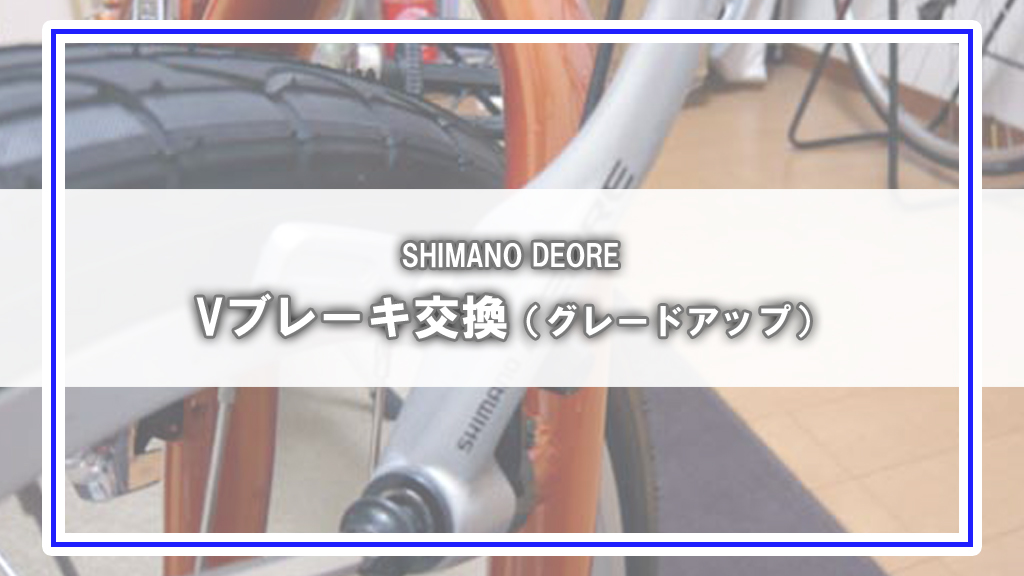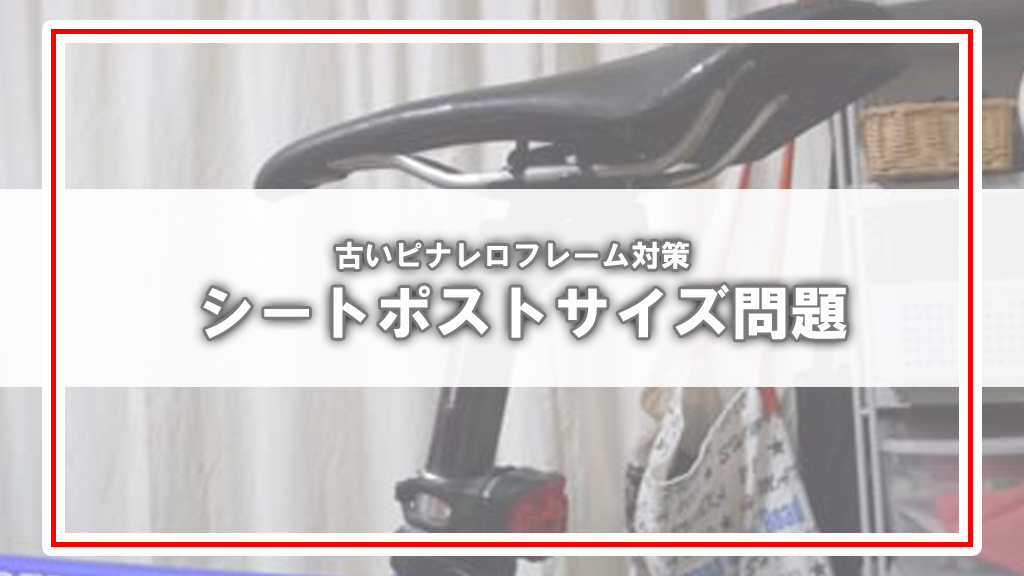【自転車DIY】STIレバー&ハンドルバー装着の基本とコツ|握り心地と操作性を左右する“見えない差”

「ハンドルとSTIレバーの取り付けなんて、簡単でしょ?」
そう思っていたら、左右のズレ・角度の違和感・ケーブルの取り回しミスなど、“あとで気になる”ポイントが次々と出てくるのがこの作業。
この記事では、ドロップハンドルとSTIレバーを正確に取り付けるための基本手順と、実際にやってみて気づいた“ちょっとした工夫”をまとめました。
この記事でわかること
- ハンドルバーの取り付け手順と“クロス締め”の基本
- 左右バランスの確認方法と、水平器の活用ポイント
- STIレバーの取り付け位置と“ズレ防止”のコツ
- 作業中に起きた“納得いかない”あるあるとその対処法
- ケーブル通し前にやっておくべき“最終チェック”
はじめての自転車組立
今回は、自転車の操作に必要なパーツの取り付けに挑戦しました。
ハンドルバーの取り付け
まずはハンドルバーを装着します。
最初は、STIレバーを先に取り付けてからステムに装着しようかと考えましたが、何となく違和感があったため、ハンドルを先に取り付けることにしました。
ネジの締め付けはクロス順で行う
ネジを締めるときは、左上を締めたら次に右下を締める、といったようにクロスする順番で行うのが基本です。

基本を守ることの重要性
この方法は、自分でもいつも基本としてしっかり守っています。
ハンドルの左右バランスを確認する
ネジを締める前に、ハンドルの左右の長さをしっかり揃えます。

測り方の基本は?
測り方はこのような感じで行いましたが、正確かどうかははっきりしません。
それでも、大きなずれはないと思います。たぶんですが。
水平器で角度を確認する
ドロップハンドルの下側が水平に見えたため、レベルメーター(水平器)を使って確認してみました。

正確さには限りがあるかも
自転車がしっかり固定されていないため、あくまで感覚的な確認です。
単に持っていたので試してみた、というのが正直なところです。
STIレバーの取り付け
次に、STIレバーの装着を行います。

左右の確認は必須
左右を間違えないように注意しましょう。
見ればすぐに判断できるので、しっかり確認してください。
バンドの取り付け
バンドが外せたので、まずバンドをハンドルに通してから、レバー本体を取り付けました。

5mmアーレンキーの使い方
レンチを差し込む穴は、レバー本体の外側にあるカバーゴムの隙間にあります。
ガイド溝で位置調整が簡単
カバーを少しめくると、ガイド溝が見えて分かりやすいです。

レンチで軽く締めた後、位置を調整してからしっかり固定します。
両側の取付けイメージ
両側に装着すると、このような状態になります。

左右の高さ調整が必要
この時点で左右の高さが異なっていたため、バランスを見ながら調整を行いました。
最後まで納得できないズレ
ケーブルを通す段階まで、左右のズレが気になっていました。
“握り心地は、取り付けで決まる”——STIレバー&ハンドルバー装着で快適な操作性を手に入れる
今回の作業では、ハンドルバーとSTIレバーの取り付けにおいて、クロス締め・水平器・握り心地の確認など、細部にこだわることで快適性と安全性を両立することができました。
“見た目の左右対称”よりも、“実際に握ったときの違和感のなさ”を優先することで、乗車時の安心感が格段にアップ。
“締めて・握って・直して・納得する”——そんな気持ちになれる、自転車DIYの体験記でした。
ネジは“対角締め”が基本。でもそれだけじゃない
ハンドルバーの固定は、左上→右下→右上→左下の順で少しずつ締める“クロス締め”が基本。
でも、左右の出っ張り具合や角度も同時に確認しないと、あとでズレが気になることに。
STIレバーは“見た目”より“握りやすさ”優先
左右の高さが微妙に違って見えるときは、実際に握ってみて違和感がないかを優先。
水平器や目視だけで決めると、乗ったときに「なんか違う…」となることも。
“納得いかない”を放置しない
「ケーブル通したらズレてる気がする…」
そんな違和感は、バーテープを巻く前に必ず修正。
“あとで直すのが面倒”な場所だからこそ、今やっておくのが正解でした。