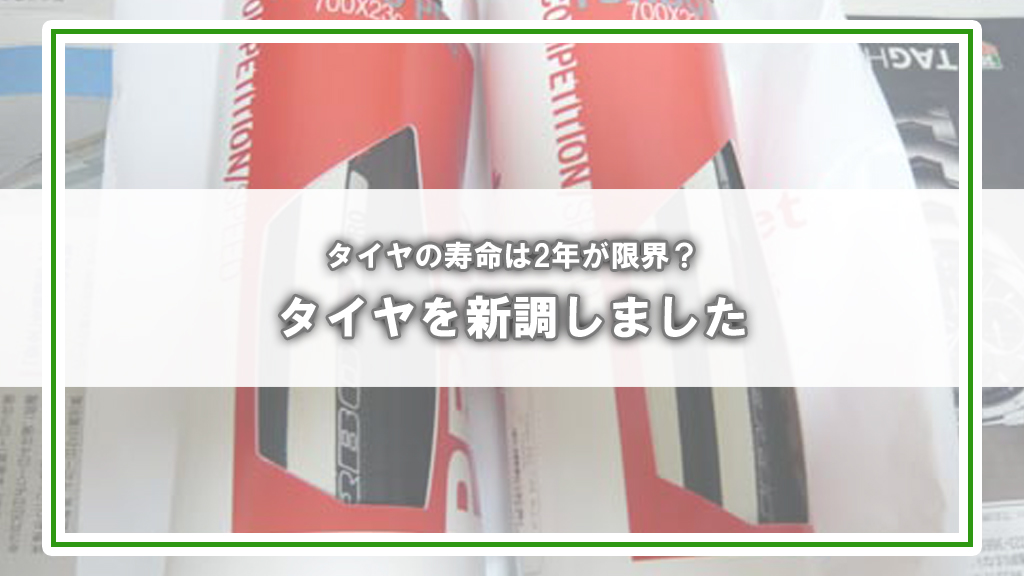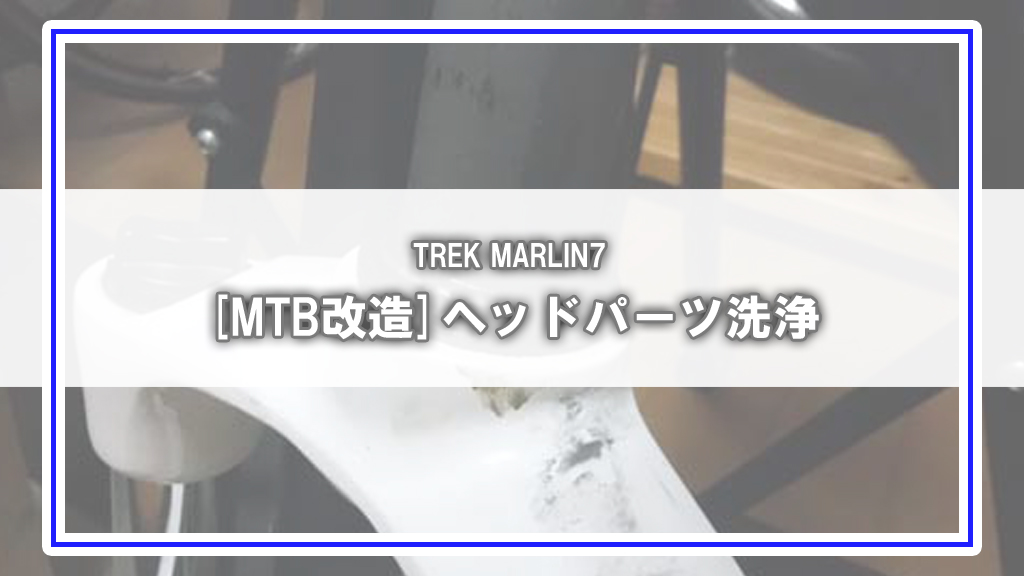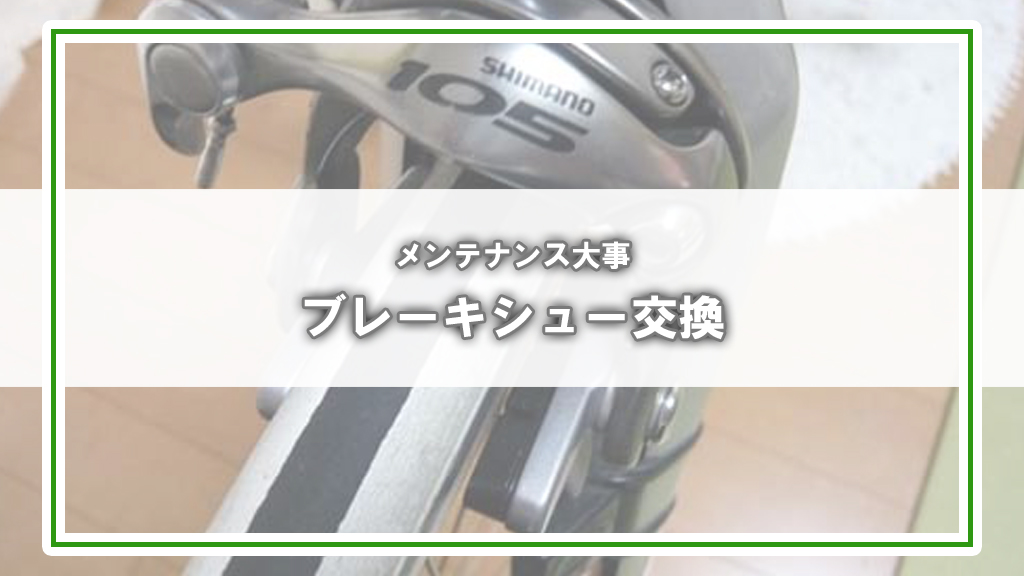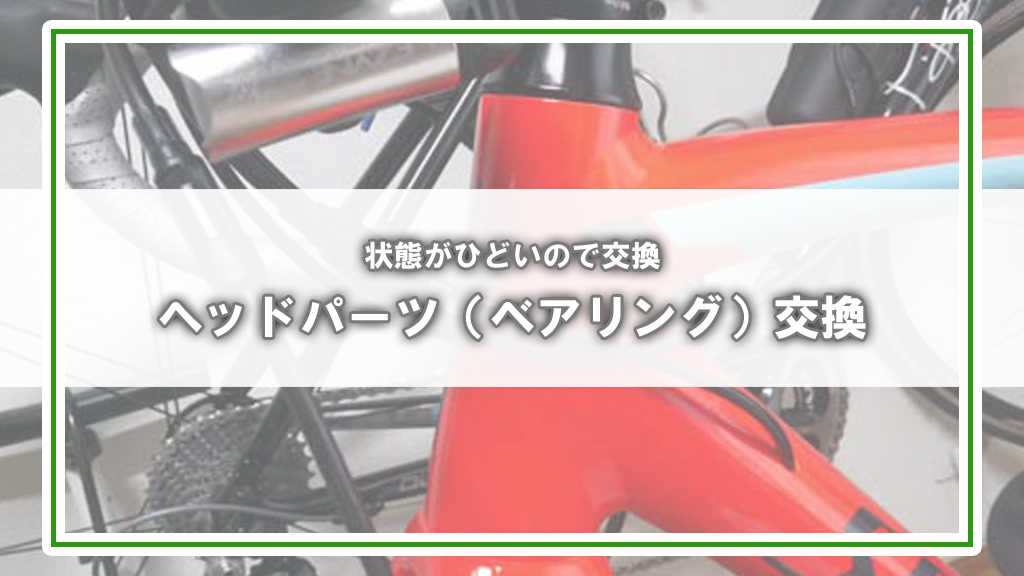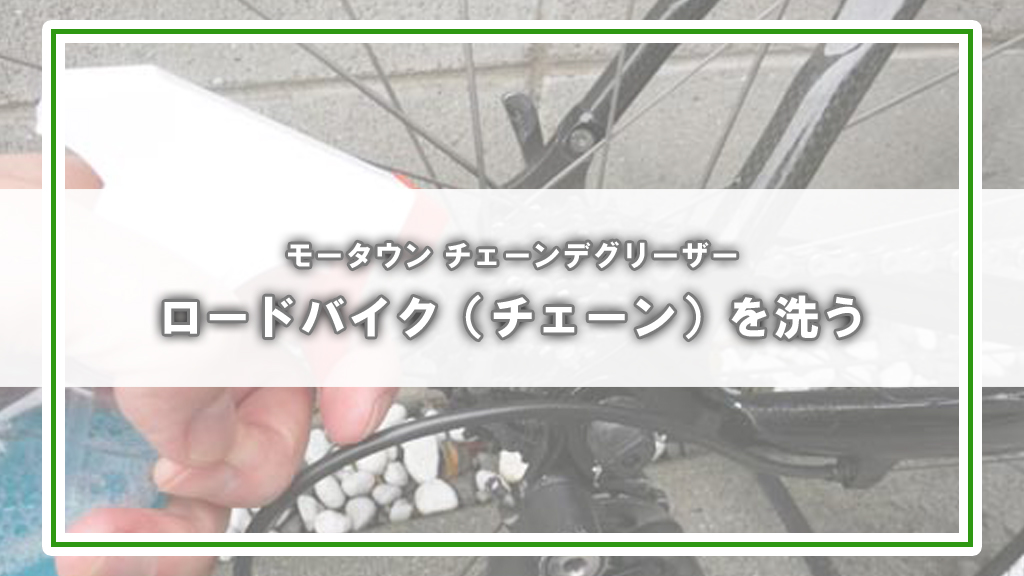捨てるには惜しい、でもこのままじゃ乗れない——革サドル再生チャレンジ!

「お気に入りだったけど、もう限界かも…」
そんな状態のサドルを前に、今回は革の張り替えに初挑戦しました。
対象は、セライタリアのSLR XP。表面の革はボロボロ、ウレタンも劣化寸前。
でも、ベースはまだしっかりしている——ならば、もう一度“乗れるサドル”に蘇らせてみよう!
まずは、練習用にジャンクのロールスサドルで張り替えをテスト。
その経験を活かして、いよいよ本命のSLR XPに取りかかります。
使用したのは、LOKIPA製の合皮レザーとステンレス製のネジ類。
下地を傷めないよう慎重に革を剥がし、半年寝かせた構想を形にする作業が始まりました。
この記事でわかること
- 革サドルの張り替えに必要な道具と素材
- 練習用サドルでのテストとその成果
- 実際の張り替え手順と仕上がりのコツ
- DIYならではの“味”と、再生後の乗り心地
- 「直して使う」ことの楽しさと満足感
サドル再生計画
自転車仲間から譲り受けたセライタリア SLR XPのサドルですが、革がかなりボロボロになっています。
今回はこのサドルの革をできるだけ復活させることに挑戦してみます。

この記事は2014年に複数回に分けて投稿した記事をまとめたものです
修理方法の検討
サドルの革がボロボロになっているため、張り替えをすれば再び使える可能性があります。
情報収集
ネットや書籍で修理方法を調べてみると、なんとルイヴィトンの革を使ってサドルを張り替えた体験談もあり、驚きました。
こうした情報を参考に、実際の作業を検討していきます。
材料購入
修理に必要な革と接着剤を用意するため、東急ハンズで材料を購入しました。
これで作業の準備は整い、張り替えに取りかかれそうです。

端切れ牛革・接着剤:約1200円
クラフト系のものは東急ハンズで大体揃う
テスト用サドルの準備
まだ使えそうなボロボロのサドルでいきなり修理するのは不安だったため、テスト用に不要なサドルを探しましたが、家には見当たりませんでした。
ジャンクサドルを探す
そこで失敗を避けるため、ヤフオクでジャンク品のサドルを購入することに。
まさに「目的と手段を見誤る」典型的なパターンかもしれませんね。
セラ・サンマルコ ロールスをヤフオクで購入
ヤフオクでタイミングよく、有名なサドル「セラ・サンマルコ ロールス」のジャンク品を手に入れました。
落札金額+送料:約1,000円
予想以上のボロボロ具合
ジャンク品と承知していましたが、予想以上に状態が悪く、かなり傷んでいました。

屋内作業禁止に
このサドルの状態を見た相方さんから、室内での開封や作業を禁止されてしまいました。
レストア1回目スタート
練習用として用意したボロボロサドルと革が揃ったので、いよいよ作業を開始します。
上記理由に寄り、屋外での作業を予定しています。
古い革の剥がし作業
ボロボロになっていた古い革は、ヤスリを使って削り取る方法を選びました。

手で丁寧に剥がすよりも、ヤスリで削った方が早く、きれいに処理できました。
剥がした後の状態
古い革を削り終えると、思ったよりもフレームがきれいな状態でした。
ただ、黒ずんでいる部分はカビのようなので、もう少し丁寧に削って処理する必要があります。

金具の取り外しとクリーニング
革を剥がす作業と前後しますが、サドルの金具は可能な限り取り外して、錆び取りやクリーニングを行います。

取付方法の検討
錆びて劣化したパーツは元の状態に戻せないため、代替の方法や部品で取り付ける方法を検討しています。
金具のクリーニング
錆が浮いているので、それを落とします

真鍮製
この時代のサドルは真鍮パーツだったので、表面の錆を溶かしてみます
金属の錆び取り
錆び取りには「サンポール」が効果的だと考えていますが、100円ショップで買った代用品でも使えるか試してみました。

漬け置き処理
適当な容器に水と溶剤を入れて、金属を漬け置きします。すると泡が立ち始め、効果に期待が高まります。

ミスの発覚
しかし、代用品として買った製品は「塩素系」だったため、いくら待っても錆は取れませんでした。
やっぱりサンポールを購入
代用品は諦めて、酸性タイプの「サンポール」を購入しました。使用時は「混ぜるな危険」の表示があるので、体に付かないよう十分注意が必要です。

混ぜるな危険の酸性タイプ(体に付かないように注意)
再び漬け置き作業
先ほどと同様に容器に入れて漬け置きしました。少し錆が落ちた気がしますが、漬け置き時間が短かったのか完全には落ちませんでした。

少し落ちた気がするが、漬け置き時間が短った
室内持ち込み禁止
相方さんから、目につく場所にサンポールの容器(ボトル)を置くのは許せないと言われ、屋外の物置に保管することになりました。
結局、力技で対応(錆取り失敗)
サンポールによる錆取りは残念ながら効果が不十分で、錆を完全に落とすことはできませんでした。
そのため、コンパウンドやピカールを使って手作業で磨き落とすことにしました。
革を張る作業開始
金具の処理はほどほどにして、いよいよサドルに牛革を貼り付けていきます。
接着剤で簡単固定
適当な大きさにカットした牛革の裏面に接着剤をたっぷり塗り、サドルの形に沿わせてしっかり固定しました。

多少の違和感はあるものの、自分としては綺麗に貼れたと自画自賛しています。
(作業に集中していたため、細かい作業写真は撮れていません。)
試行錯誤の連続
特に難しかったのは、サドル先端部の革が寄りやすい部分の処理ですが、目立たない部分なので適当にごまかしました。

粗さはご愛敬
素人の手作業なので細かい部分は雑ですが、全体としてはおおむね綺麗に貼り付けることができました。
金具の取り付け作業
先に綺麗にしておいた金具をサドルに戻していきます。

リベットの代わりにネジを使用
リベットが手に入らなかったため、代わりにネジで固定する方法を採用しました。
M3ネジの選択
M3ネジがサイズ的にちょうど良く、ステンレス製で質感もサドルに合っていると思います。
サイド部:M3×10mmボルト
センター部:M3×20mmボルト
裏面の処理
ネジでボルト止めしているため、裏側にネジが飛び出しています。

リアパネルの裏はよく手が触れる場所なので、怪我防止を考慮しました。
ビニールテープでカバー
適切な素材が見つからなかったため、裏側のネジ部分をビニールテープで覆いました。

目立たない場所なので、この方法で問題ないと判断しました。
サイドパネルの加工
朽ちてしまったサイドパネルの取り付け部分を再利用できるように処理を行いました。

朽ちた突起部の削り取り
再利用不可能な突起部分をヤスリで平らに削り取り、次のロゴ復活作業の準備をしました。

文字の復活(エンボス処理)
文字部分はエンボス加工になっているため、赤色のペンキを凹部に流し込みました。
その後、表面の余分なペンキを削り取り、文字がはっきり見えるように仕上げました。成功と言える状態です。

M3皿ネジの取り付け
サイドパネルの裏側にM3×10mmの皿ネジを瞬間接着剤で固定しました。

サドルへの取り付け
革の元の穴位置に合わせて穴をあけ、サイドパネルを取り付けました。

ナットで固定
裏側からナット止めでしっかり固定し、触れる部分ではないため特別な養生はしていません。

完成
修理・加工を終えたサドルを、少しクラシックな雰囲気のBD-1に取り付けました。

スエード生地を使用したことで、肌触りが非常に良く、快適な座り心地になっています。
レストア2回目(いよいよ本番)
ジャンク品のセラ・サンマルコ「ロールス」で練習を重ね、なんとか形になったことで、本命の作業に取りかかります。
事情があってテスト後、半年ほど作業が止まっていましたが、今回は目的だった「セラ・イタリア SLR-XP」の革張り替えに挑戦します。
このサドル、形状もフィーリングも自分にとってベストなので、うまく再生できれば現役復帰も夢じゃありません。
作業前|白サドルの汚れと劣化をチェック
このサドルは本革製で、乗り心地は申し分ありません。ただし色が白いため、どうしても汚れが目立ちやすく、全体的にくすんだ印象に。
写真では写っていませんが、サイド部分には削れによる下地の露出もあり、見た目の劣化が気になる状態でした。

革を丁寧に剥がす作業
先に作業したロールスサドルとは異なり、こちらのサドルは革の状態が比較的良好。
そのため、下地のウレタンを傷つけないよう、慎重にゆっくりと革を剥がしていきました。

革を貼る作業
サドルの形に合わせて、あらかじめ革を適当なサイズにカット。
裏面に接着剤をムラなく塗り、慎重に位置を合わせて貼り付けていきます
この作業、両手が完全にふさがるので写真は断念…。
完成|やっぱりレザーは手触りが違う!
半年間の放置を経て、ようやく練習・テスト後の実践取り付け。
「まあ、こんなもんか」と思いながら貼ってみたら──意外と、いい感じに仕上がりました!

今回使ったのは加工しやすい柔らかい牛革。
そのおかげでフィット感もよく、手触りも◎。
黒レザーにしたことで汚れも目立ちにくくなった(はず)なので、実用性もバッチリです。
まとめ
お気に入りのサドルは長く使っていると表面や角が傷みがちですが、今回のレストアで新品同様とはいかなくても、十分に再生して長く使い続けられる状態になりました。自分で手をかけることで愛着も増し、これからも大切に乗り続けられそうです。
革製サドルだった場合は・・・
表面素材が革製(本革や合皮など)のサドルであれば、今回紹介したように張り替えが可能です。張り替えることで見た目をリフレッシュできるだけでなく、座り心地も改善できるため、長く快適に使い続けることができます。素材や接着剤の選び方によって仕上がりや耐久性も変わるので、慎重に選ぶことがポイントです。
作業は意外とシンプル。誰でもチャレンジできる!
古い革を剥がして、新しい革を貼る。基本的にはこれだけ。細かいテクニックもありますが、道具と手順さえ押さえれば、DIY初心者でも十分トライできます。
張り替えの手順(基本編)
1. 材料を用意する
・張り替える革(東急ハンズなどの店舗で探すのがおすすめ)
・接着剤(革用 or 多用途)
2. 古い革を剥がす
下地を傷つけないように、ゆっくり丁寧に。
3. 革をカットする
貼るサドルより少し大きめにカットしておくと安心。
4. 接着剤を塗る
革の裏面にたっぷりと塗布(説明書は必読!)。
5. 貼り付け作業
サドルの前側から貼り始め、形に沿わせながら全体に密着させる。
6. 固定&乾燥
クリップや洗濯バサミでしっかり固定。乾くまでしばらく待ちます。
7. 仕上げのカット
はみ出た部分をハサミやカッターで整えて完成!
好きなものを、できるだけ長く
自分で張り替えたサドルは、決して新品同様とはいきません。でも、不思議と「これからも長く使っていけそうだな」と感じます。手をかけた分、モノへの愛着はぐっと深まるものです。
気になったら、またレストアすればいい
革の種類によって、どのくらいの期間使えるかは違ってきます。でも、気になったタイミングでまた張り替えればいいのです。完璧じゃなくていい。自分のペースで、手を入れながら大切に使い続ける──それがレストアの楽しさだと思います。
革サドル張り替えで感じた、“直す楽しさ”と“乗る喜び”
練習は裏切らない
最初にロールスで試したことで、革の伸ばし方や接着のタイミングなど、感覚を掴むことができました。
本番ではその経験が活きて、思った以上に綺麗な仕上がりに。
合皮でも“雰囲気”は出せる
使用したLOKIPAの合皮レザーは、ライチ紋の質感が本革に近く、見た目も上々。
耐久性や防水性も期待でき、実用性と見た目のバランスが取れた素材でした。
“乗れるアート”としてのサドル
張り替えたサドルにまたがって走り出した瞬間、「これはもう、ただのパーツじゃない」と実感。
手をかけたぶんだけ、愛着も深まる——そんなDIYの醍醐味を味わえました。