【続・修理記】SPDシューズの靴底を完全復活させた結果|補修材と実用性のリアルな話
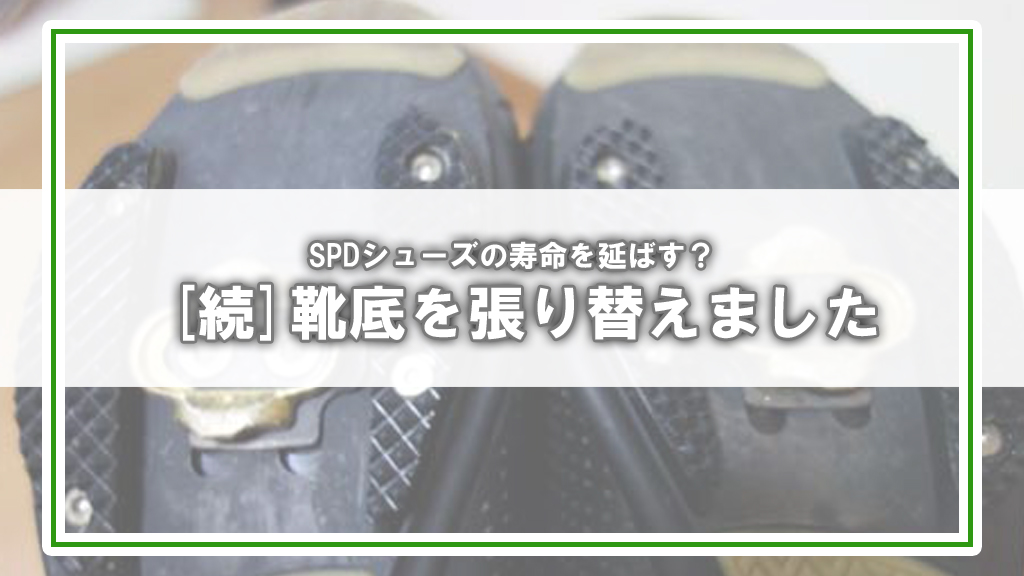
前回の「SPDシューズ靴底補修」から数ヶ月。実走で使いながら経過を観察していたところ、ある改善点と“気になる部分”が見えてきました。
今回は、補修後の様子・使って良かった材料・ダメだった点など、リアルなアフターフォロー記録をお届けします。
同じように「靴底補修して長く履きたい」と考えている方の参考になればうれしいです。
前回の修理は“応急処置”だった?実用性を見直して再チャレンジ!
前回DIYで修理したSPDシューズの靴底ですが、実際に使ってみるといくつかの問題点が浮き彫りに。
接着の甘さやソールの厚み、ネジ穴の位置ズレなど、実用面での不具合が目立ってきたため、再度修理を行うことにしました。
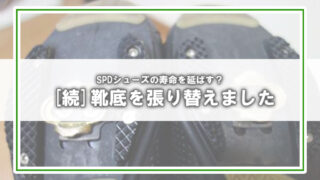
再修理に踏み切った理由
- 歩行時にソールの端が浮いてきてしまった
- クリートの装着感が左右で微妙にズレていた
- ソールの形状が足裏の動きに合っていなかった
“一度やってみたからこそ分かる”改善ポイント
DIY修理は、やってみて初めて気づくことが多いもの。
今回はその経験を活かして、より実用性と耐久性を重視した再修理に挑戦しました。
材料選びの落とし穴|柔らかすぎる素材は“崩壊”の原因に
前回のDIY修理で使用した靴底素材は、柔らかくクッション性のあるタイプ。
一見すると歩きやすくて良さそうに思えたのですが、実際に使ってみると耐久性に難あり。
数回の使用で、ソールが崩れたり、削れたりといった劣化が目立つようになってしまいました。

素材を“硬質ゴム”に変更|耐久性重視の再修理へシフト!
前回の柔らかいソール材では、クッション性はあるものの耐久性に難ありという結果に。
そこで今回は、クッションのない“硬質ゴム素材”に切り替えて再修理を行うことにしました。

硬質ゴムを選んだ理由
- 摩耗に強く、削れにくいため、歩行やクリートの着脱に安定感が出る
- クッション性はないものの、SPDシューズ本来の“踏み込み感”を損なわない
- ソール形状が崩れにくく、再加工や再接着にも強い
補修材の選定ポイント
| 比較項目 | 柔らかい素材 | 硬質ゴム素材 |
|---|---|---|
| クッション性 | 高い | ほぼなし |
| 耐久性 | 低め(削れやすい) | 高い(長持ち) |
| 加工のしやすさ | カットしやすい | 少し硬めで要注意 |
| 実用性 | 歩きやすいが劣化しやすい | 歩行時に安定感あり |
再修理スタート|前回の反省を活かして“実用性重視”の作業へ
今回は、前回の修理と同じ手順をベースにしつつ、素材と仕上がりにこだわった再修理を行っていきます。
作業内容はシンプルですが、素材が硬質ゴムに変わったことで、加工や接着の精度がより重要になります。
再修理の基本ステップ(前回と同様)
- 古いソールの取り外し
- 接着面をきれいに剥がし、残った接着剤や汚れを除去
- 新しいソール材のカット
- 元のパーツより一回り大きめにカットし、貼り付け後に整形
- ネジ穴の加工
- キリで下穴を開け、ポンチで8mmの穴を打ち抜く
- ※下に板を敷いて作業するのが鉄則!
- 接着剤で圧着
- 硬質ゴムは反発力があるため、圧着時間をしっかり確保
- 速乾タイプでも最低15〜30分は固定推奨
- 形状の微調整
- 乾燥後にハサミやカッターで形を整え、段差や角を滑らかに
傷んだ靴底を丁寧に剥がす|再修理の第一歩は“下地づくり”から
再修理にあたり、まずは前回取り付けた靴底パーツを丁寧に剥がす作業からスタート。
接着剤の残りや変形したソールをそのままにしておくと、新しい補修材がしっかり密着せず、再び剥がれる原因になってしまいます。

ソール材をカットして貼り付け|2回目の作業はスムーズに!
再修理ということもあり、今回は作業の流れやコツを把握していたため、かなりスムーズに進行。
ソール材は大まかなサイズでカットし、貼り付け後に微調整するスタイルで対応しました。

使用した道具一覧(再確認)
| 道具 | 用途 |
|---|---|
| はさみ | ソール材の大まかなカットに使用 |
| 接着剤(速乾・強力タイプ) | ソールと靴底の圧着固定に使用 |
| 穴あけポンチ(8mm) | クリート用のネジ穴を開けるため |
| 金づち | ポンチの打ち込みや圧着時に使用 |
接着剤は靴底専用の強力タイプを選ぶことで、剥がれにくく長持ちする仕上がりに。
ポンチ作業時は、下に傷んでもよい板を敷くのが鉄則です!
形を整えて、DIY修理完了!“貼ってからカット”が美しく仕上げるコツ
ソール材を貼り付けたあとは、不要な部分を丁寧にカットして形を整えれば完成です。
この工程で仕上がりの美しさと実用性が決まると言っても過言ではありません。

綺麗に仕上げるためのポイント
- 先に貼ってからカットする
- ソール材を“型に合わせてから貼る”のではなく、少し大きめにカットして貼り付けた後に整形する方が、ズレや歪みが出にくくなります
- ハサミやカッターで丁寧に整える
- 角を丸めたり、段差を滑らかにすることで、引っかかりや剥がれのリスクを軽減
- 左右のバランスを確認しながら微調整
- 見た目の左右差があると、歩行時の違和感につながるため、仕上げは慎重に
まとめ|壊れても“また直せばいい”と思える気軽さがDIYの魅力
今回の再修理を通じて感じたのは、**「靴底の補修って、思ったよりずっと簡単」**ということ。
もちろん、また壊れる可能性はゼロではありません。
でも、必要な道具さえ揃っていれば、1時間もかからずに再修理できる。
そう思えるだけで、お気に入りのSPDシューズを気兼ねなく履き続けられる安心感があります。
DIY補修のメリットを再確認
- 廃盤モデルでも自分の手で延命できる
- 修理のたびに自分の技術と知識がアップデートされる
- 「また壊れても直せばいい」という前向きな気持ちになれる








