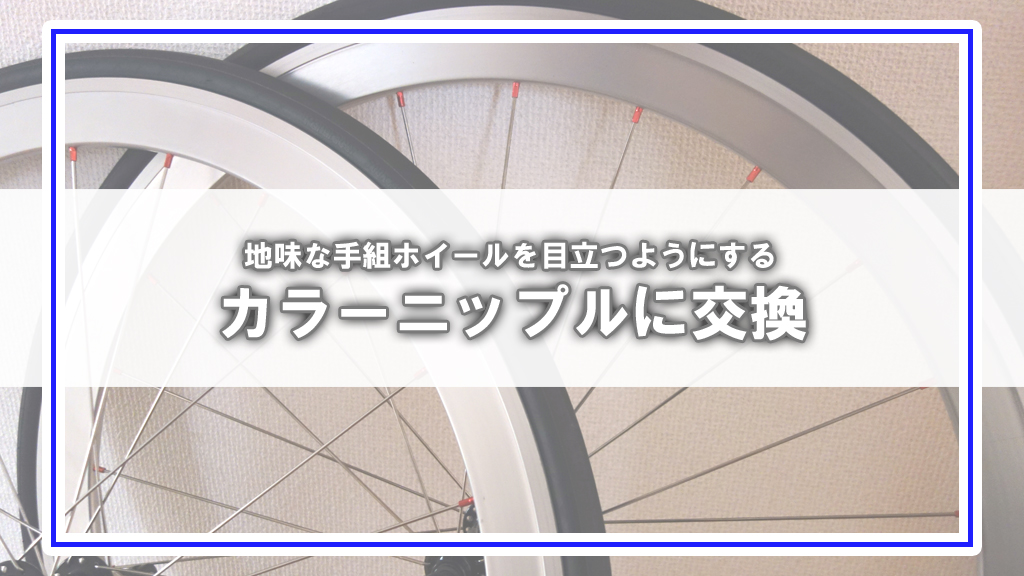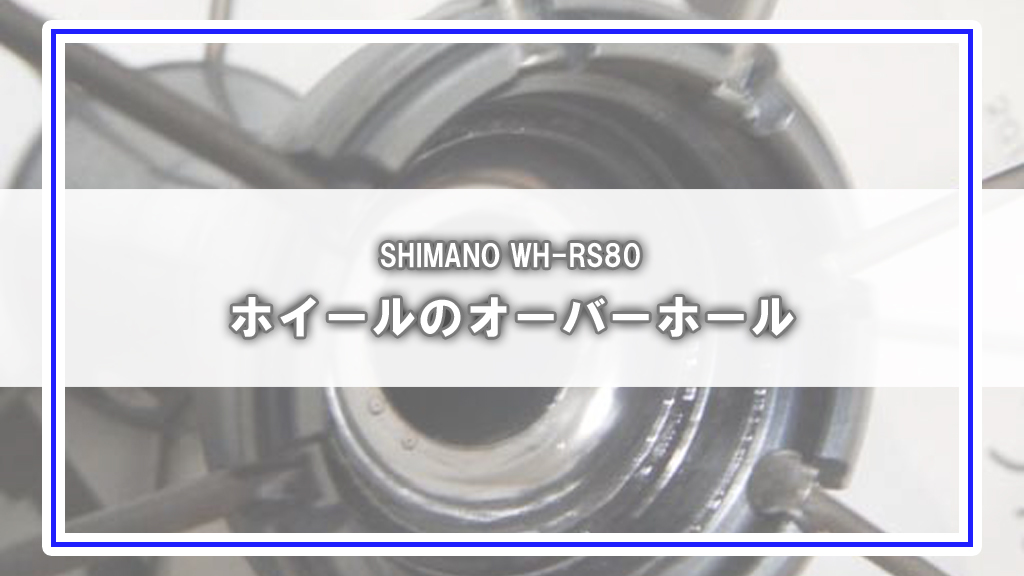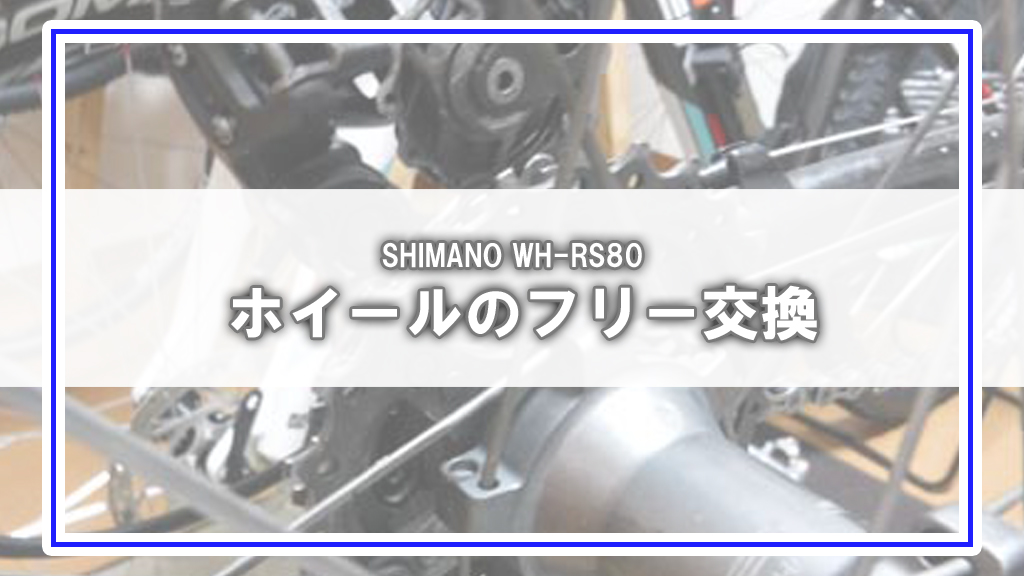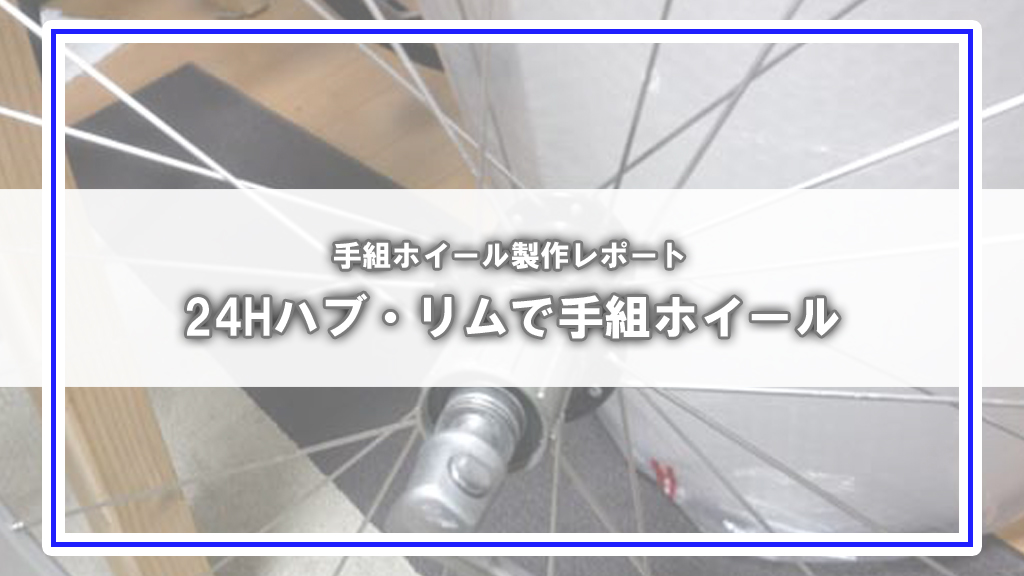【旧車レストアDIY】126mmエンドのクロモリロードを蘇らせる!シマノ105ベースでハブ自作&調整記録
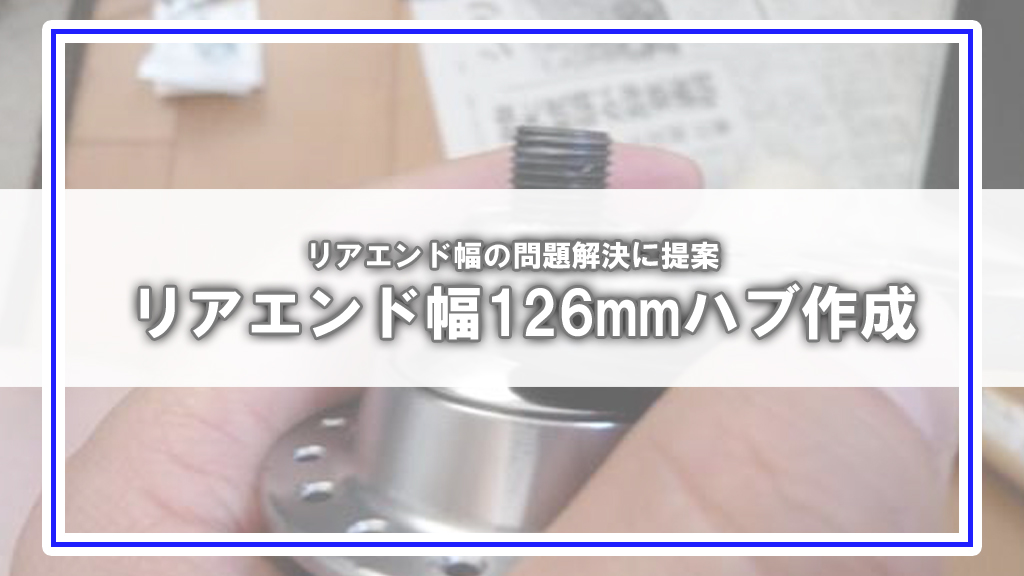
美しいラグ、細身のパイプライン…手に入れた憧れのヴィンテージ・クロモリフレーム。ここに、信頼性の高い現行のコンポーネントを組み込んで、最高の“ネオレトロ”マシンを創り上げたい。
しかし、そこで全てのレストア好きが直面する、厚く、高い「壁」があります。それは、旧規格の「エンド幅126mm」と、現行規格の「ハブ幅130mm」という、わずか4mm、されど絶望的な4mmの差です。
フレームを無理やり広げる「エンド拡げ」は、最後の手段。では、どうする?
この記事では、そんなレストアの聖域に踏み込む、禁断の、しかし最もスマートな解決策を徹底解説します。現行のシマノ105ハブをベースに、アクスルを組み替え、ホイールを再調整することで、126mmフレームに完璧に適合するハブを“自作”するという、究極のDIYです。
これは、ただのパーツ交換ではない。ヴィンテージバイクに、新しい魂を吹き込むための、挑戦の記録です。
レトロフレームレストア必須技術
レトロと呼ぶくらい古いフレームをレストアしようと思うと、高確率で遭遇する問題が、リアハブの長さが現在の規格より短いです(2013年に書いた記事ですが、この話も規格が古くなっています)
古い規格フレームでも、少しの工夫すれば新しいホイール使用可能
リアエンド126mmのフレームに対応
DAHON ROUTEのパーツをグレードアップしようと計画
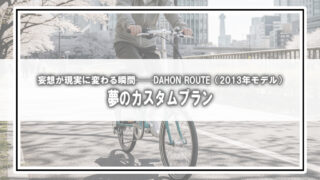
リアエンド幅126mm
リアエンド幅が現行130mmより短い126mmでした
鉄フレーム
クロモリフレームなので無理やり広げて対応させることも可能ですが、寿命が短くなりそうなので、126mm長ハブを作ってみました
リアハブ長一覧表
- リムブレーキ(現行):130mm
- リムブレーキ(オールド):126mm(120mmもある)
- ディスクブレーキ(クイック仕様):135mm
- クロスバイク・MTB(カンチブレーキ仕様):135mm
シマノ製はエンド幅加工可能(FH-5700)
DURA-ACEより下のグレードのハブ(2013年まで確認)は、ハブ軸を交換可能

ハブの左側のスペーサーを交換すれば、リアエンドの長さを調整することができます
ハブ入手について
今回の作業でのリアハブ対応状況
グレード低め
グレードの低いものしか新品ハブは手に入りません
ヤフオクなどで中古品を探す方が良いかもしれません
電動化
10速のDi2は外装(バッテリーなどは外付け)なので、ハブ幅が126mmのオールドフレーム(1970年代)で、電動コンポーネント(7900、6700シリーズ)を装着可能になります
ケーブルなどはタイラップ止めや圧着テープなどで固定すれば、見た目もスッキリします
11速化
残念ながら、5800以降は、スペーサーがボディ一体成型になっているので、交換は難しい
※当然、12速化も無理です
軽量化
32Hハブと24Hリムの組み合わせで、ホイール重量を軽量化できます

エンド幅126mm加工
加工作業を行います(多少の誤差はOKくらいの気持ちで)
- 座金の購入(スペーサー代用品)
- 反フリー側(スプロケットなし側)のスペーサー交換
- 玉当たり調整
- フレームに装着(長さが合わない場合の対処法)
スペーサー調整
都合のよいスペーサーを見つけることができなかったので、ホームセンターで見つけた座金(ワッシャー)を代用品でつかってみました

105(FH-5700)スペーサー:6mm
購入した座金は、日本製なのでパッケージ記載通り2.7mmでした

1mm弱は多少の誤差は大丈夫だろうと、完璧を求めず作業を続行しました

ハブ軸は大体真ん中になるように位置調整して、玉当たりを調整しました

フレームに取付
あっさりとフレームに収まり、問題なく使用できました

フレームに合わない
リアエンドの幅が薄くて、ハブ軸が余る場合は、座金をスペーサー代わりにして、フレームの外側に挟んでください
レストアはクロモリ
126mmハブが必要なレストアバイクは、ほぼ間違いなく鉄フレーム(クロモリ)なので、少しぐらいの誤差で、フレームが狂わないと思います(断言できませんが・・)
カスタム・まとめ
古いフレームになるので素材は鉄(アルミやクロモリ)がほとんどです。多少はハブの締め付けで調整できます
完璧を求める人には向いていませんが、こういう方法もあるんだと参考にしてください
DIYで広がる、レストアの可能性
“フレームを守る”という選択肢
古いクロモリフレームは、素材のしなやかさゆえに130mmハブも入ることは入ります。
でも、フレームに無理をさせず、ハブ側で対応するという発想は、レストアの美学とも言えるかもしれません。
スペーサー選びは創意工夫の見せどころ
専用パーツが手に入らないなら、代用品で工夫するのもDIYの醍醐味。
今回はM10サイズのバネ座金をスペーサー代わりに使用し、フレーム外側に挟むことで調整しました。
“ちょっとのズレ”を許容できるのがクロモリの強み
126mmのフレームは、ほぼ間違いなく鉄製。
だからこそ、1〜2mmの誤差にも柔軟に対応できる懐の深さがあります。
もちろん断言はできませんが、今回の加工ではフレームの狂いもなく、無事に装着できました。
工具大事
メンテナンス・加工作業を行う場合、工具(道具)は良いものを選んだ方が作業が楽になります

イレギュラー
手組を行う場合、32Hのハブが手に入りやすいですが、ホイールを少しでも軽くするために2:1組も試しています

まとめ
今回は、ヴィンテージ・クロモリフレームを現代のコンポーネントで蘇らせる上で、最大の難関である「126mmエンド幅問題」を、現行ハブの改造によって克服する一部始終をご紹介しました。
シマノ105ハブからアクスルとスペーサーを抜き、寸法を詰め、そしてホイールのセンターを出し直す。地道で精密な作業の末に、旧時代のフレームと新時代のコンポーネントは、完璧に結ばれました。
この挑戦的なDIYから得られた、3つの確かな手応えを共有します。
- レストアの神髄は「創造」にあり 市販パーツをただ組み合わせるのではなく、存在しないなら「創り出す」。現行の信頼性と、旧車の美しさを両立させるこのハブ改造こそ、レストアという趣味の最も奥深く、楽しい部分です。
- ハブの改造は、ホイールの「再構築」と共にある ハブ幅を詰める作業は、必ずホイールの「センター出し(振れ取り)」とセットです。この2つをやり遂げて初めて、バイクはまっすぐ、そして美しく走ります。ハブの分解組立と、ホイールビルドの知識が、ここに見事に融合します。
- 最高の“いいとこ取り”が、ここにある クロモリフレームが持つ、しなやかで時代を超えた乗り心地。そして、現行コンポーネントが提供する、ストレスフリーで正確無比な操作性。この二つの時代の“良いところ”だけを享受できること。これこそが、この困難な作業の末に得られる、最高のご褒美です。
4mmの壁は、決して乗り越えられないものではありません。この記事が、あなたのガレージで眠る、美しいヴィンテージフレームを再び現代の路上へと解き放つ、その勇気と知恵の一助となれば幸いです。